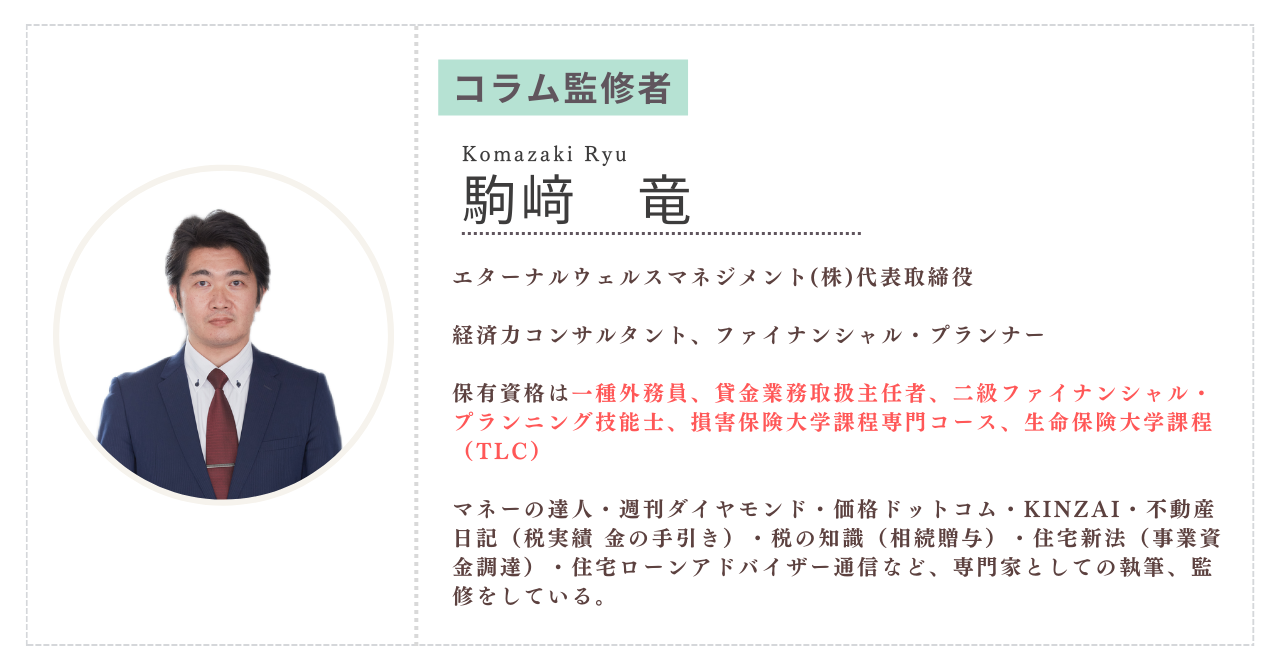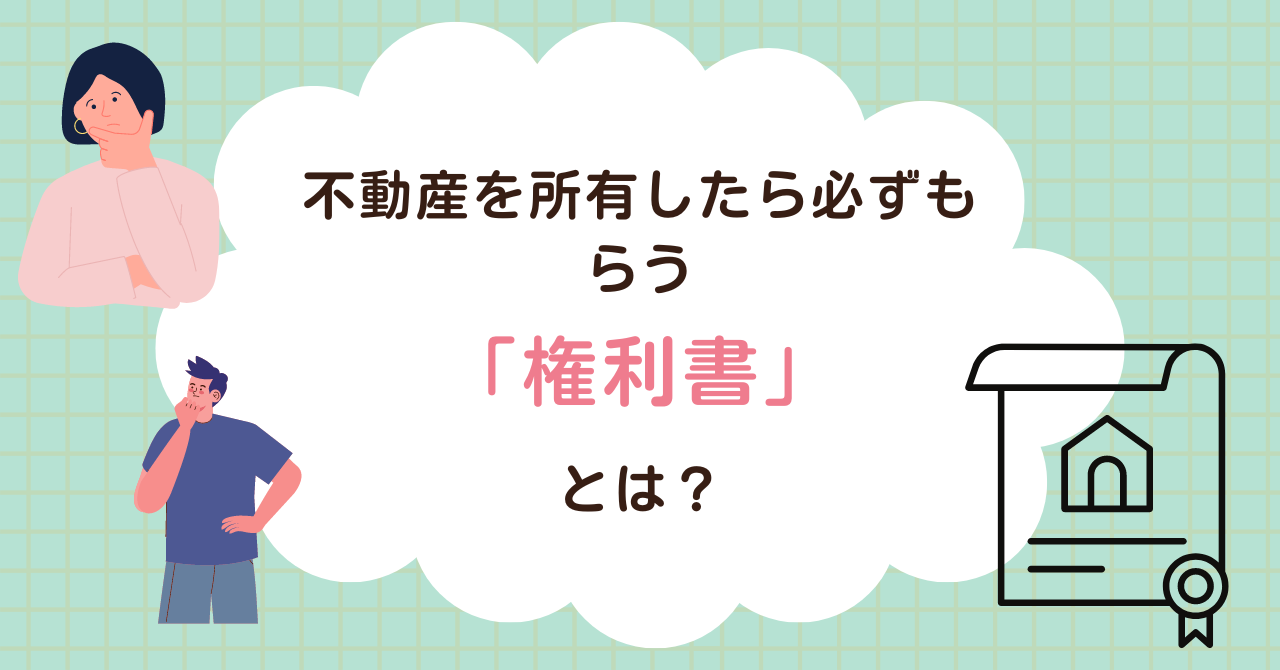
ドラマやニュースなどで、家や土地の「権利書」という言葉を耳にすることがあります。権利書が大切なものだとは分かるものの、なぜ大切なのか、どんな時に役立つのかご存知でしょうか。
改めて、権利書とはどういうものなのか、よく知っておきましょう。
不動産の権利書には、どんなことが書かれている?

土地や建物といった不動産を購入した際には、法務局で「この人が所有者になりました」という所有者移転登記登記を行います。すると、2004年までは「登記済権利書」が発行されていました。
権利書には、不動産の住所や種別、面積、所有者名などが記され、法務局の朱印が押されています。「権利書を持っている人が、不動産の所有者である」という、本人確認書類の一種と考えると分かりやすいでしょう。
権利証は紙に印刷されたものなので、必用な時には原本を提出しなければいけません。これではインターネットでのオンライン手続きをする際に困ってしまいます。
そのため法務局のオンライン化にともない、2004年までで廃止となりました。代わりに登場したのが「登記識別情報」です。
登記識別情報は、12桁の英数字を組み合わせたパスワードのようなものです。不動産の所有者には、不動産の住所や所有者名、登記識別情報を記した「登記識別情報通知」が発行されます。
登記識別情報通知は、パスワード部分に情報保護シールが貼られていたり、袋とじになっていたりして、使用したかどうかがすぐに分かるようになっています。パスワードはそのくらい大切なものなのです。
権利書も登記識別情報も、使い道はほぼ同じと考えていいでしょう。そのため現在でも、登記識別情報通知を「権利書」と呼ぶことがあります。
権利書は紛失しても再発行してもらえない

権利書(登記識別情報通知)が必要になるのは、不動産の売却や譲渡の時です。住宅ローンの借り換えや、不動産を担保にしてお金を借りる場合にも、必要になることがあります。
ただ不動産を相続する場合は、基本的には権利書を必要としません。なぜなら、戸籍や遺産分割協議書といった相続に必要な書類で、不動産の相続人であることが証明できるからです。
権利書(登記識別情報通知)は使う頻度が非常に低いので、「気がついたら紛失していた」「どこにしまったのか分からない」といった事態になることも決して珍しくありません。
気をつけなければいけないのは、紛失した場合でも再発行はしてもらえないことです。
もちろん、権利書(登記識別情報通知)をなくしたからといって、不動産の所有権が失われてしまうわけではありません。ドラマなどでは犯罪者が「権利書をよこせ!」と迫ることがありますが、実はあまり意味のない行為といっていいでしょう。
不動産取引にはほかにもさまざまな書類が必要なので、権利書(登記識別情報通知)だけで所有移転登記がされてしまうこともありません。ただ、犯罪者が盗んだ権利書を不動産詐欺などに使うこともあるので、注意が必要です。
また、権利書(登記識別情報通知)を紛失した場合も、不動産の売却や譲渡に差し支えることはありません。弁護士や司法書士に依頼して本人確認の面談を行い、権利書の代わりとなる本人確認書類を作成してもらうことで不動産取引ができます。
ただ、権利書(登記識別情報通知)をなくしてしまうと、不動産の売却や譲渡の際に余分な時間や手間がかかってしまいます。やはり権利書(登記識別情報通知)は大切に保管しておいたほうがいいでしょう。
余談ですが、登記識別情報通知を再発行してもらえるケースがあります。それは、パスワードに貼られた情報保護シールがきれいに剥がせず、パスワードが読めなくなってしまった場合です。
登記識別情報通知が発行され始めた初期には、情報保護シールの質が悪く、長年のうちに剥がせなくなってしまうことがありました。そのため、特例として再発行できるようになったのです。
登記識別情報通知の情報保護シールや袋とじは、情報漏洩の予防対策です。登記識別情報通知を受け取った際には、不動産の所有者であってもパスワードを見たりせず、そのまま保管しておきましょう。