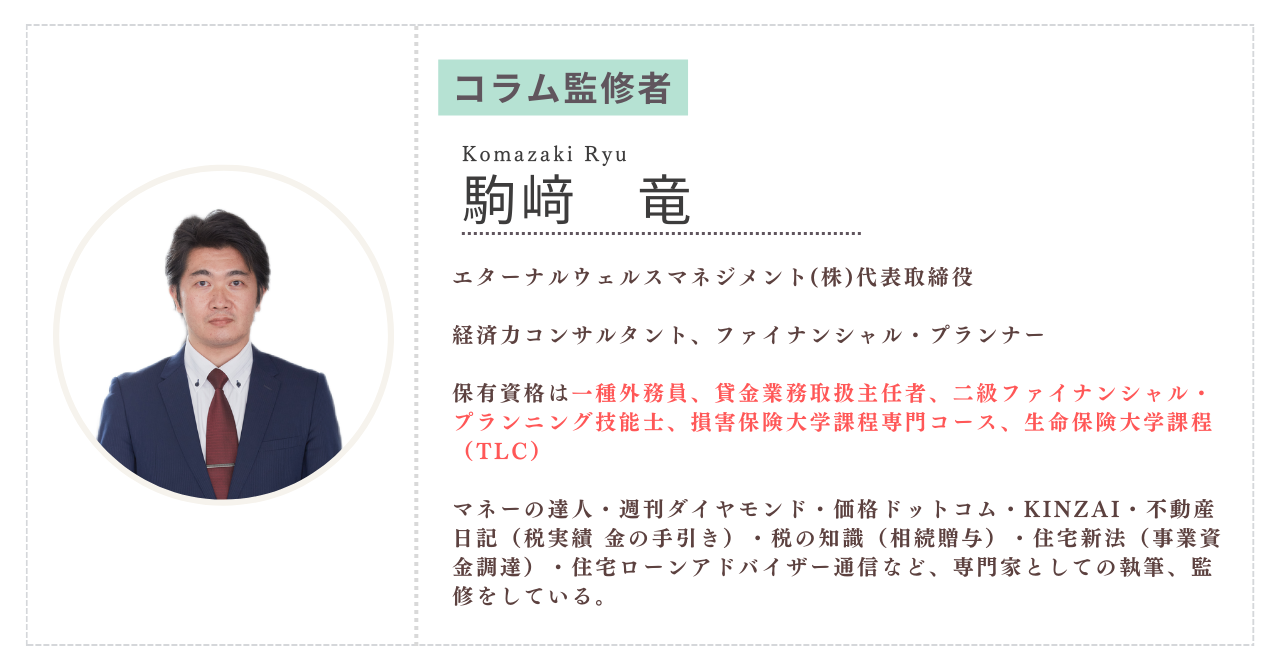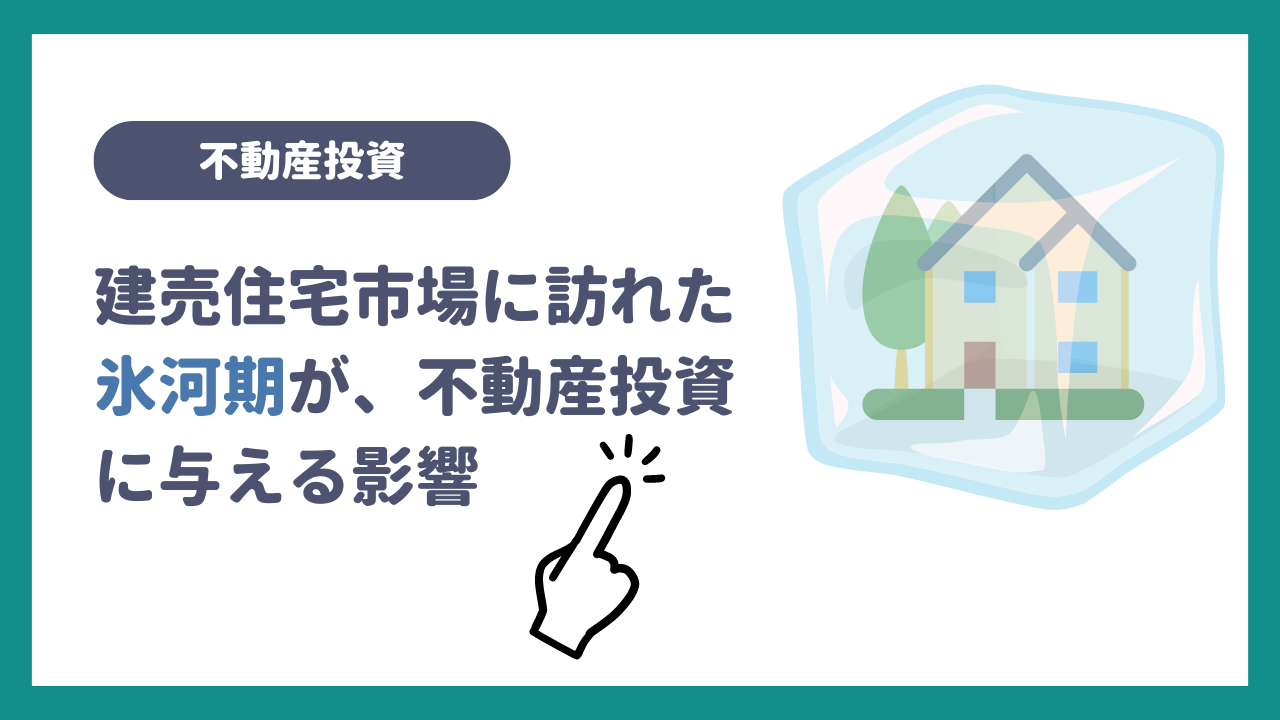
住宅市場では今、建売住宅の売買が鈍化しています。その傾向は都市郊外に顕著で、「建売氷河期」とまでいわれているほどです。
なぜこんな状態になってしまったのでしょうか。また建売住宅の鈍化によって、不動産業界全体にどんな影響があるのでしょうか。詳しく見てみましょう。
建売住宅が氷河期といわれるほど売れない理由

建売住宅の在庫過剰は、すでに2023年当初から始まっていました。住宅メーカーの決算報告を見れば、誰の目にも明らかです。
建売住宅市場で国内シェアの約3割を占める飯田グループホールディングスでは、2023年4~12月期の決算で純利益が前年同期比53%減。2024年3月期決算でも、前期比59%減という大幅な下方修正となりました。
この大幅減益について飯田GHDでは、建売住宅の市場が振るわず住宅の在庫が増えたため、販売価格を調整して早期売却に取り組んだ結果だと説明しています。
2020年からの新型コロナウイルスの蔓延で、外出が敬遠され、リモートワークが推奨されるようになりました。都市部に出勤しなくてもよくなったことから、郊外の広めの建売住宅の人気が高まり、価格も急激に高騰したのです。
現在の建売住宅の冷え込みは、その反動が原因のひとつと見られています。さらに、コロナ禍で滞っていた経済活動が次第に復帰してきて、ローン金利も上昇傾向にあります。
例として、住宅金融支援機構などが提供する住宅ローン「フラット35」を見てみましょう。2023年1月時点での借入金利水準最は1.3%でしたが、2024年1月時点では1.94%となっています。
加えて、さまざまな物品が世界規模で高騰していること、円安によって輸入コストが増加していることから、国内物価の上昇傾向も止まりません。これでは住宅の購買意欲が減退してしまっても当然といえるでしょう。
建売氷河期によって不動産業界全体が不安定になる

建売住宅市場の急ブレーキは、不動産業界全体に大きな影響を与えます。
建売住宅の在庫が増えれば、在庫を抱えるハウスメーカーの負担も増大します。住宅在庫を早めに売却しようと、価格の値引き競争が激化することでしょう。
しかし、住宅資材も物価高の影響を受けて高騰しています。新たな住宅を作るためにかかる費用は増えているのに、住宅を売って得られる利益はどんどん少なくなっているのです。
これでは、体力のないハウスメーカーは保ちません。この状況が続けば、再編や倒産となる企業も出てきます。不動産業界が不安定になれば、不動産取引が鈍化するため、国内の経済活動全体にも悪影響を及ぼします。
この傾向は、短期的に解決することは難しいでしょう。そもそも建売氷河期にはさまざまな要素が絡んでいるため、すべてが解決方向に向かうことはあり得ないからです。
ただ、希望的な要素もあります。マンション市場は、分譲マンション、1棟マンション、新築、中古を問わず、好調な売買状況が続いていることです。
その現状を踏まえると、今後は、立地のいい物件は高値で取引され、立地があまりよくない物件はさらに価格が下落するという「二極化」がさらに進むのではないでしょうか。
不動産業界が不安定になっている今、不動産投資でも、価格が安いからといって安易に手を出すのはおすすめできません。また、所有物件の出口戦略についても、改めて考え直す必要があるでしょう。