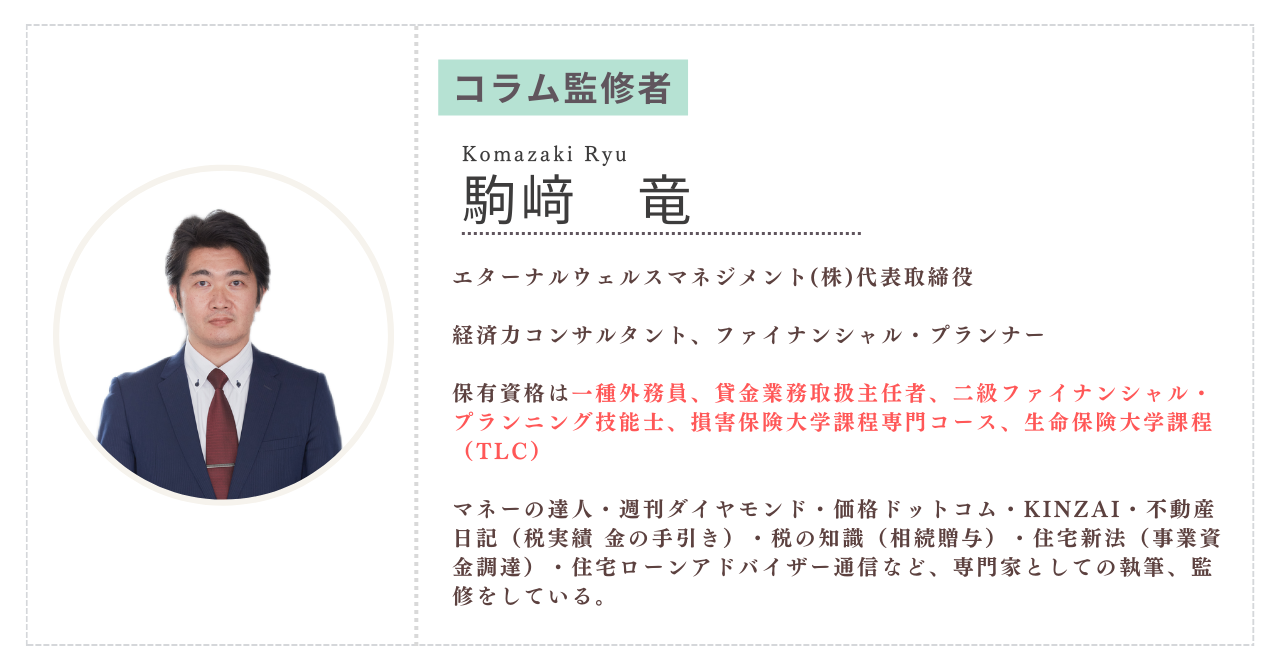近年、JR東日本をはじめとする鉄道各社が、さまざまな子育て支援を打ち出しています。その動向は、不動産業界からも注目されています。
鉄道会社の動向は、ともすれば不動産業界に大きな影響を与えるものです。その理由や、鉄道会社の子育て支援事業で注視すべきポイントを解説しましょう。
鉄道会社の動向によって不動産の価格が変動する

そもそも鉄道会社と不動産業界には、切っても切れない縁があります。
交通の便がいいエリアは不動産の価格も高くなり、交通の便が悪いエリアの不動産価格は下がります。その「交通の便」の中心を担っているのが鉄道会社だからです。
鉄道会社としても、利用客数が多くないと収益につながりません。そのため、駅前にスーパーマーケットを建てたりして利便性をさらに向上させ、沿線の住民を増やす努力をしています。
利便性が高いエリアほど住みたいと思う人が増え、不動産の価格は上がります。つまり、鉄道会社の動向が不動産価格を決めるカギとなっているのです。
近年では、鉄道各社が子育て支援を打ち出しています。以前は子育て支援といっても、駅の中に授乳スペースを作ったり、親子イベントを開催したりといった、直接的には沿線住民を増やすことにつながらないものばかりでした。
その中で、注目すべき子育て支援策が登場しました。鉄道の高架下に、保育園や学童保育所を建設するケースが増えてきているのです。
保育園や学童保育所といった保育施設は、収益につながりにくい事業として知られています。なぜ鉄道各社が、保育施設の建設に積極的になっているのでしょうか。
不動産業界にもメリットのある高架下の保育施設

日本には2022年時点で、3万2442ヵ所の踏切があります。踏切は鉄道事故の多発ポイントとなっているため、国としても以前から踏切を立体交差にする事業を推進していました。
その支援のひとつが、線路を高架にする費用の2/3を、国や自治体が補助するというものです。ただ、公的補助を受けるためには、「跡地の15%を公共目的に使用する」というルールがあります。
踏切の立体交差にはいくつかの方法がありますが、費用が一番安上がりなのが、線路を高架にする方法です。線路を高架にすると、元の線路が走っていた高架下の土地が空き地となります。
ルールでは、その空き地の15%を公共目的に使用しなければいけません。しかし、高架下は日照もよくないため、これまでは公園や駐車場くらいしか活用できていませんでした。
ところが、JR東日本が2010年から取り組んでいる「HAPPY CHILD PROJECT」の一環として、高架下に保育園を設置しました。これが成功したことから、ほかの鉄道会社も高架下に保育施設を設置することに積極的になったのです。
近年の建築技術なら、高架下に建物を設置しても、電車の走行音はほとんど気になりません。保育施設は、近隣住民から騒音の苦情が出ることも多いのですが、そもそも「高架下はうるさいもの」と思われているため、保育施設から出る騒音が問題になることもありません。
高架下は駅にも近いため、そもそも利用者にとっては非常にアクセスがいい場所です。こうしてみると、高架下の保育施設は非常にメリットが多いことが分かるでしょう。
保育施設が充実すれば、周辺地域に若い世代の住民が増えます。すると地域の活性化につながり、駅の利用客も多くなります。
立体交差の事業費を補助してもらえる上に、本来の鉄道事業の収益アップも期待できるのですから、鉄道各社が高架下の保育施設に積極的になるのも当然といえます。
そして、エリアの人気が高くなれば、土地の価格も上がります。言い換えれば、踏切の立体交差化計画を察知して、その詳細を知れば、今後値上がりするだろうエリアを予測できるのです。
鉄道会社の子育て支援策によって、不動産業界も大きな影響を受けることがお分かりいただけたでしょうか。不動産投資を行う上では、これからの鉄道会社の動向にも気を配っておきたいものです。