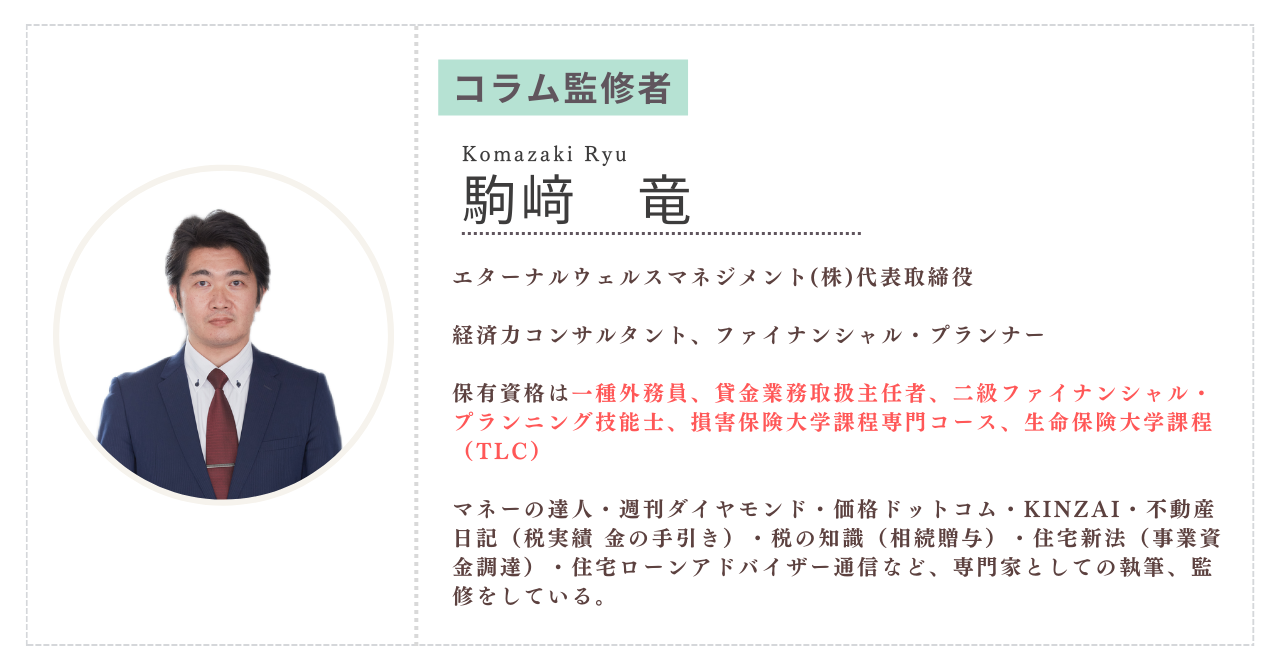2024年(令和6年)の地価公示価格が、3月26日に発表されました。全国の全用途平均で2.3%上昇と、3年連続で上昇を果たしただけでなく、2023年の1.6%と比較して上昇幅も拡大しています。
上昇率だけで見ると約30年ぶりの高い水準となっていますが、その背景にはどんな要因があるのでしょうか。今後の見通しも含めて、分析してみましょう。
公示地価の上昇は経済活動が活発になった証
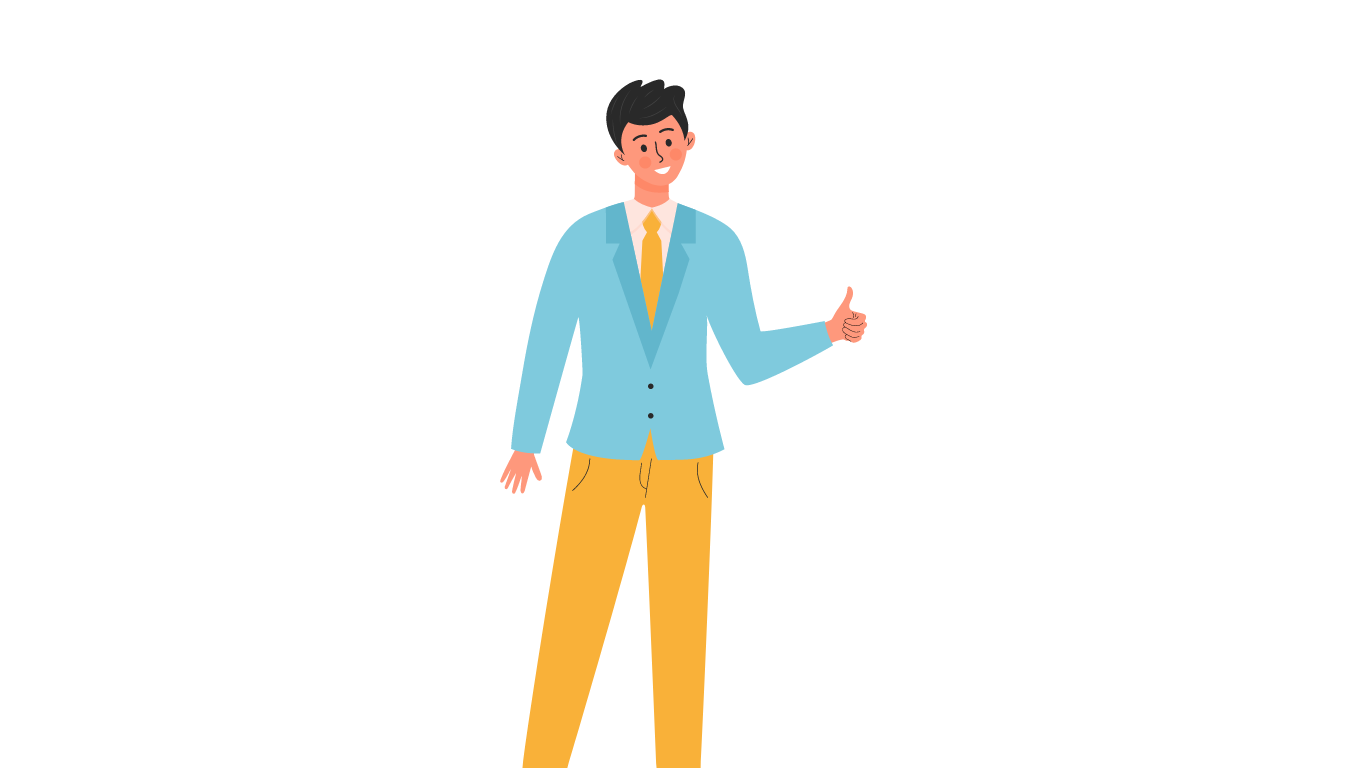
地価公示価格とは、全国2万ヵ所以上の土地の価格について地価公示法に基づいた調査を行い、国土交通省が発表するものです。毎年1月1日時点の土地の価格が、3月下旬に発表され、土地取引の基準価格として活用されています。
2024年の公示地価の全国平均を見てみましょう。住宅地が2.0%上昇、商業地が3.1%上昇、住宅地・商業地・工業地・その他など全用途平均で2.3%上昇となっています。
地価の上昇傾向は2022年から出ていました。しかし、前年2023年の上昇率は、住宅地が1.4%、商業地が1.8%、全容と平均で1.6%だったことを考えると、公示地価が飛躍的に上昇していることがうかがえます。
その背景としてはまず、新型コロナウイルス感染症についての法律上の取り扱いが2類から5類に移行し、経済活動が復活してきたことが挙げられるでしょう。
経済活動が正常化してきたことで、都市部のへの転入者も増えました。その結果、都市部の地価が大幅に上がり、全国平均を引き上げているという傾向も見られます。
東京では全用途平均で4.0%、名古屋では3.3%、大阪では2.4%の上昇にとどまりますが、札幌・仙台・広島・福岡の地方4市では、なんと7.7%の上昇となっています。
加えて、円安による訪日外国人観光客の増加もあります。日本政府観光局によると、2024年3月の訪日外客数は308万1600人で、1ヵ月間の記録としては初めて300万人を超えました。
こういったさまざまな要因が絡み合って、公示地価の上昇という形で現れているのでしょう。
バブル期のような先行買い付けによる地価上昇に注意

今後の状況を予測するに当たって、注目すべきポイントがあります。それは、市町村別の公示地価上昇率ランキングです。
1位が熊本県大津町で17.83%、2位が長野県白馬村で17.11%、3位が北海道千歳市で15.06%と、都市圏をしのぐ上昇率を見せています。17位の熊本県合志市までが10%超えとなっていますが、その中には北海道の市町が7ヵ所もランキング入りしています。
3位にランクインした北海道千歳市は、次世代半導体メーカーを目指すラピダスが新工場設置を決めた都市です。千歳市とその周辺地域での公示地価上昇は、その影響と見ていいでしょう。
1位の熊本県大津町も、台湾の半導体メーカーTSMCの熊本工場が2024年2月に稼働となりました。それが公示地価の上昇率トップとなった要因と見られています。
しかし北海道では、そういった企業や工場の進出予定がない地域でも、公示地価の上昇が見られます。たとえば北海道富良野市は、住宅地だけを見れば前年比27.9%の大幅な上昇がありました。
富良野は確かに観光地としてよく知られる場所ですが、いくら訪日観光客が増えたといっても、それだけで地価が上がるとは考えにくいでしょう。
通常なら、観光客が増えただけでは、住宅地の地価は上がりません。増加した観光客に対応するため、周辺の宿泊施設や商業施設の就業人数が増え、住宅需要が増加して、はじめて住宅地の地価が上昇するのです。
ところが富良野では、そういった流れもなく住宅値の地価だけが上昇しています。これは、土地の需要が増して地価が上昇したのではなく、「今後は地価が上がるだろう」という期待値による先行的な買い付けによるものだと考えられます。
こうした先行買い付けは、バブル期によく行われていたことです。現在の経済状況から考えても、一部地方都市の地価上昇傾向が長期的に続く可能性は低いといえます。
期待値による先行買い付けで起こった地価上昇は、突然、何の前触れもなく下降に転じることがあります。土地の購入を考えるなら、目先の数値だけではなく将来的な展望まで踏まえて検討しましょう。