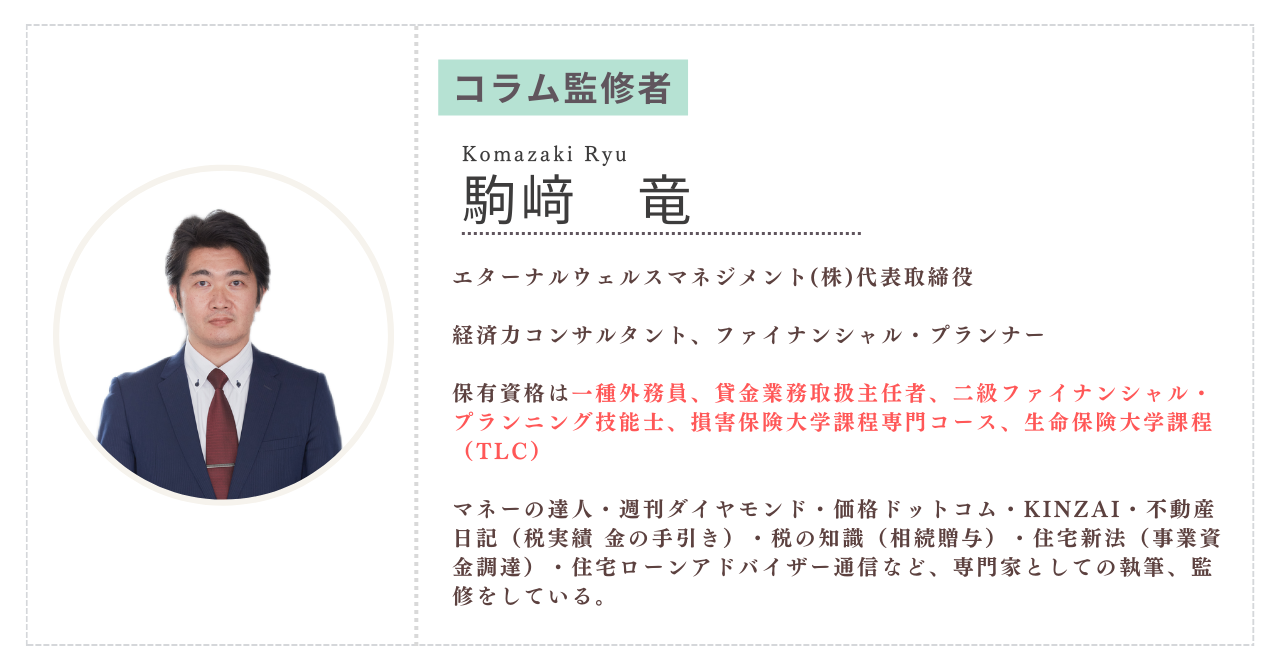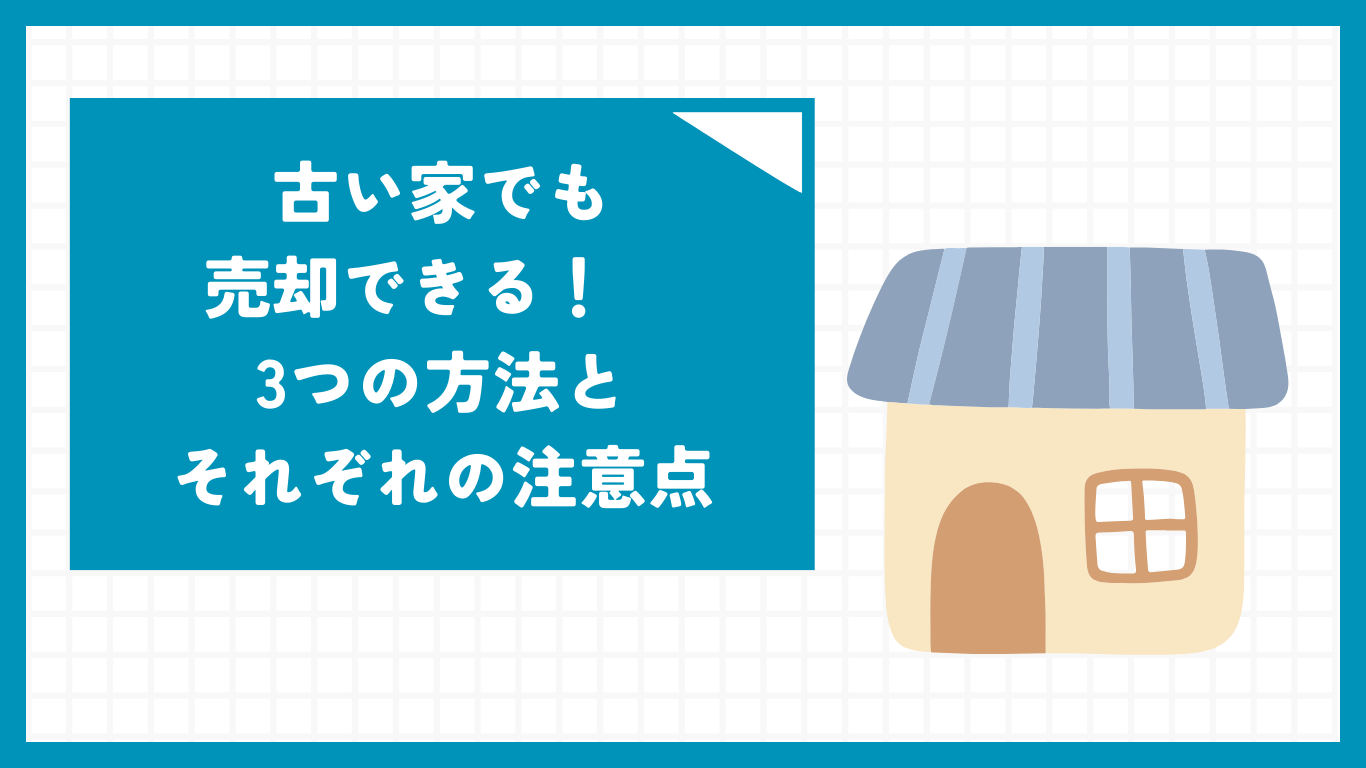
相続などで、必要のない古家を所有してしまうことがあります。建築から長い年月を経て劣化し、不具合も出ているような古家は、売却も難しいのではと思うことでしょう。
人が住めそうにない古家であっても、方法によっては売却できます。考えられる3つの売却方法をご紹介しましょう。
古家は更地にして売るか、そのまま売るか

古家の売却方法として考えられるのは、「更地にして売る」「そのまま売る」「リフォームして売る」の3つです。
古家そのものに価値はなくても、土地には高値がつくことがあります。そういった場合は、家を解体して更地にすることで、早期売却が見込めます。
ただ当然のことながら、古家の解体費用は売主負担となります。解体費用の相場は、木造住宅が坪単価2~4万円、鉄骨造が坪単価3~4万円、鉄筋コンクリート造が坪単価4~6万円となっています。
解体費用の坪単価に延床面積を掛けることで、解体にかかるおおよその金額が分かるでしょう。たとえば木造2階建て住宅で、延べ床面積が40坪なら、解体費用は80~160万円となります。
解体費用が出せない場合は、「そのまま売る」ことを考えましょう。「そのままではとても売れそうにない」と思うかもしれませんが、不動産広告を見ていると「売地(古家あり)」といった物件は決して珍しくありません。
古家を解体して更地にしてしまうと、土地が欲しい人だけがターゲットになります。一方、古家付きの土地なら、古家に一時的に住んでから解体して、新しい家を建てたいといった人もターゲットになるので、購買層が広がるというメリットがあるのです。
ただし土地だけが欲しい人は、解体費用の負担を嫌って寄りつかないことも。そのため古家付きで売る場合は、更地にして売るより価格を下げることが一般的となっています。
「そのまま売る」ことには、固定資産税が変わらないというメリットもあります。固定資産税は、土地と建物の両方にかかっているので、建物を解体してしまえば建物分だけ固定資産税が安くなると考えるかもしれません。
しかし土地にかかる固定資産税は、居住用の建物が建っている場合のみ、200平方メートルまでは6分の1、200平方メートルを超える部分は3分の1にするという軽減措置がとられています。
建物を解体してしまうと固定資産税の軽減措置が受けられないので、税額が跳ね上がってしまうことも。固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に対して請求されるので、解体する場合は土地が売れるまでの期間を考えて、タイミングを計りたいものです。
リフォームして売ることができる古家とできない古家

3つめの方法として「リフォームして売る」という方法をご提案しました。古家であっても、土台や柱などがしっかりしている場合は、リフォームすれば一般的な住宅として売却できる可能性があります。
ただ中古住宅の購入希望者は、購入後にリフォームしてからの入居を考えていることも少なくありません。そのため売主側でリフォームするポイントを絞っておかないと、リフォーム費用がムダになってしまいます。
売主がまずリフォームすべきポイントは、家の耐震性です。現在の建築基準法では、震度6~7程度の揺れでも倒壊しない耐震性が求められています。
耐震性の低い建物だと、住宅ローンの審査が通りにくい傾向があります。購入希望者が現れても、住宅ローンが通らなければ買ってもらえないことでしょう。
耐震性を高めるリフォームは、工事費用も高額になります。「リフォームして売る」という手段がとれるかどうかは、古家の状態や売主の経済状態によると考えておきましょう。
古家をどう処分するか決めかねて、そのまま放置しておくのは絶対におすすめできません。少なくとも、敷地に生える雑草を刈り取る、家を換気するといった最低限の維持管理はしておきたいものです。
古家の維持管理を怠っていると、ゴキブリやシロアリなどの害虫が大量発生したり、ネズミやハクビシンといった害獣の巣になったりすることもあります。その被害が近隣に及んでクレームになってしまうと、さらに売りにくくなることも考えられます。
また「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、近隣に悪影響を及ぼす「特定空家」や、特定空家になる恐れのある「管理不全空家」は、土地に対する固定資産税の軽減措置が受けられなくなると定めています。
自治体から「特定空家」「管理不全空家」に指定され、改善を行わないでいると、税額が跳ね上がってしまうことに。そうなる前に、古家は早めの売却を心がけましょう。