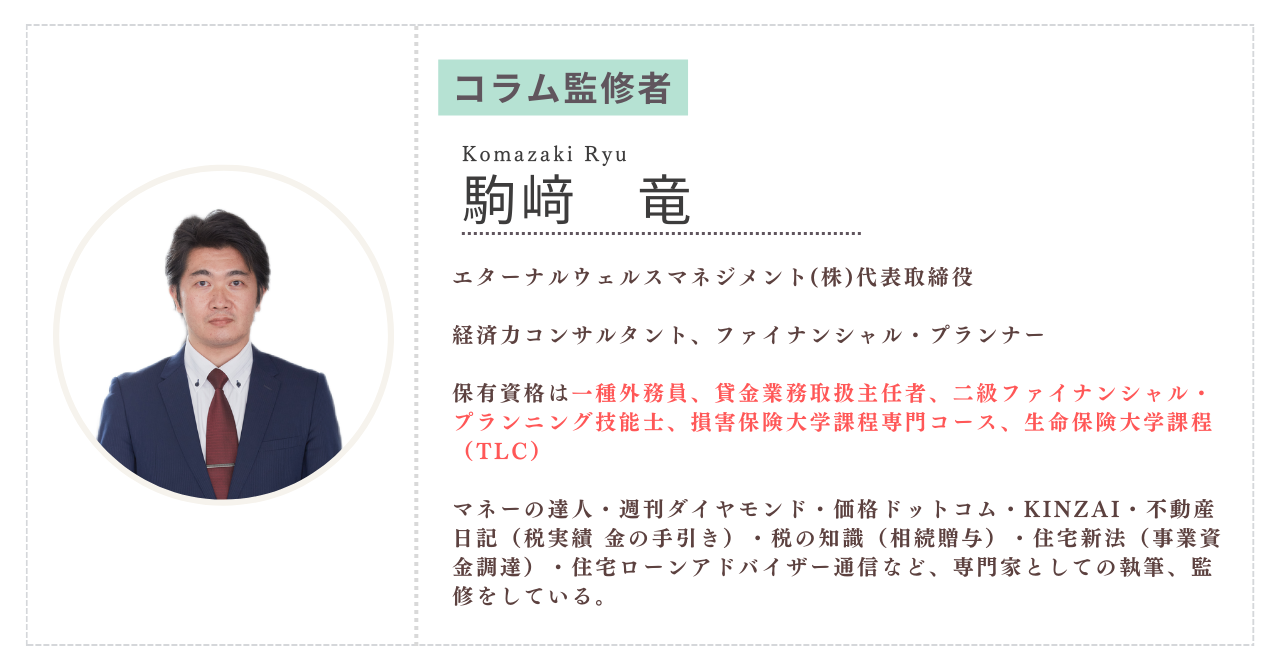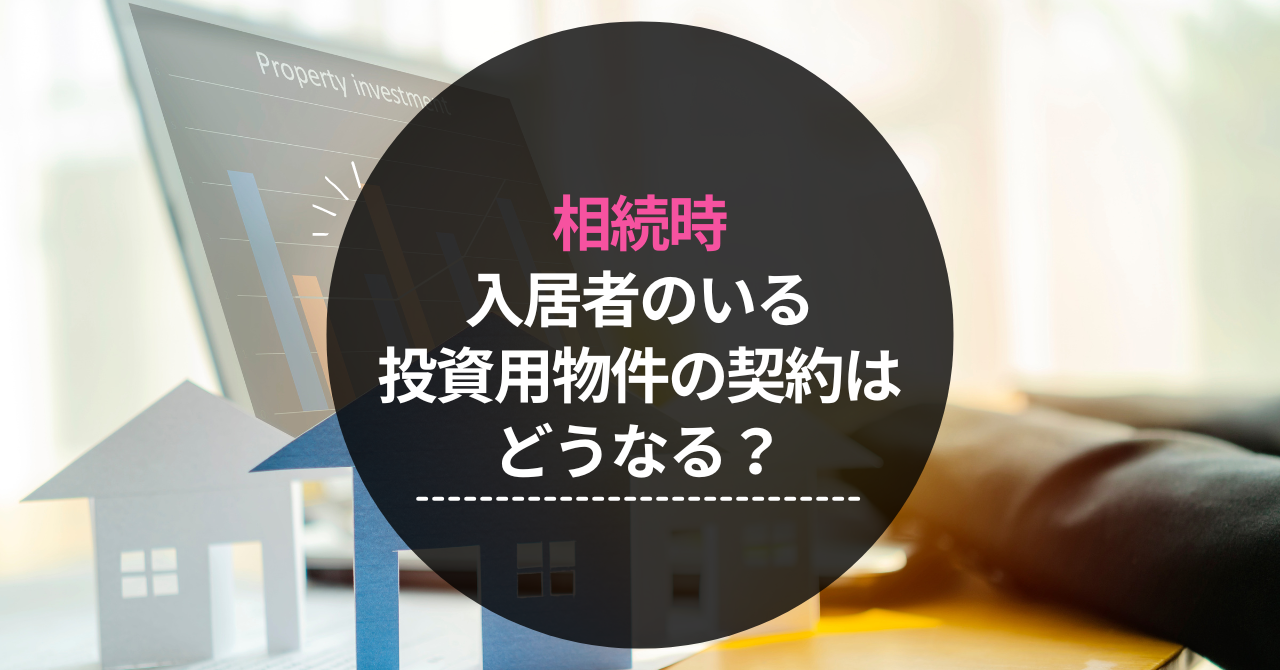
両親や親戚などが亡くなった際、投資用物件を相続することがあります。相続にあたってはさまざまな手続きが必要になりますが、相続した投資用物件に入居者がいた場合、賃貸借契約はどうなるのでしょうか。
いざという時に慌てないよう、賃貸借契約はどう引き継がれるのか知っておきましょう。
賃貸借契約は相続人にそのまま引き継がれる

投資用物件を相続した場合、亡くなった貸主と入居者が結んでいた賃貸借契約は、相続した人がそのまま引き継ぐことになります。
相続で貸主が変わることについて、入居者に許可を求めたり、同意を得たりする必要はありません。相続した後で、貸主が変更になったことを入居者に伝えるだけで済みます。
また貸主が変わったからといって、新たに賃貸借契約を結び直す必要もありません。というよりも、亡くなった貸主が入居者と結んだ賃貸借契約の内容は、基本的に変更できないと考えてください。
もし契約内容の変更や中途解約をしたい場合は、貸主側に正当な事由があることを提示して、入居者の合意を得る必要があります。正当な事由とは「貸主側で物件を使う必要がある」「賃料が相場に比べて著しく安い」といった、誰が見ても納得できる理由と考えておきましょう。
相続によって賃貸借契約を新たに結び直す必要はないといいましたが、できれば「相続があったこと」を示す覚書(おぼえがき)をつけておくことをおすすめします。
覚書とは、契約した当事者同士が同意した内容を記しておく文書です。契約書の添付資料と考えると、分かりやすいかもしれません。
新たな貸主と入居者の間でトラブルが起こった際、契約書にある名前が亡くなった貸主のままだと、相続したことを証明するなどの手間がかかることがあります。覚書を作成しておけば、その手間が省けることでしょう。
覚書に決まった書式はないので、自由に作成できます。具体的には「相続人が貸主の地位を承継したことを確認する覚書」として、日付を明記し、貸主と入居者の署名捺印をします。
覚書も契約書と同じように、内容が同じものを2通作成し、貸主と入居者で保管しておきます。契約書の添付文書なので、賃貸契約書とまとめて保管しておきましょう。
相続人が複数だった場合の契約相続の流れ

相続する立場の人が複数いた場合、遺産をどう分けるのか、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。遺産分割協議が行われている間は、遺産に含まれている投資用物件は、相続人全員で所有することになります。
ただ場合によっては、遺産分割協議に年単位での時間がかかることもあります。その間、入居者から支払われる賃料はどう取り扱ったらいいのでしょうか。
遺産分割協議の間に入ってくる賃料については、遺産とは別に計算します。どのように分配するか、法的な取り決めはありませんが、遺産の相続割合に応じて分配するのが一般的です。
ひとつ気をつけておきたいのは、賃料の振込先です。
口座の所有者が亡くなったことを知ると、金融機関は故人の口座を一時的に凍結してしまいます。すると、口座への振り込みや口座からの引き出しができなくなってしまいます。
貸主が亡くなったらすぐ、家賃振込先の口座を変更し、入居者や物件の管理会社に伝えましょう。家賃の振込先は、相続人の中から代表者を決めて、その口座を指定するのが一般的です。
その後、遺産分割協議を行い、誰が投資用物件を相続するのか決めます。相続人が決まったら、相続人の氏名や連絡先、新たな家賃振込口座を管理会社や入居者に伝えます。
もうひとつ忘れずに行いたいのが、投資用物件の相続登記です。投資用物件のある地域を担当する法務局で、相続によって所有者が変わったことを登記します。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、怠ると10万円以下の過料がかかるようになりました。それまでも義務とされてはいましたが、違反しても特に罰則はなかったため、放置されていることも少なくなかったのです。
相続登記は、所有者が亡くなってから3年間の期限内に行わなければなりません。過料で損をしないためにも、相続登記を忘れず行いましょう。