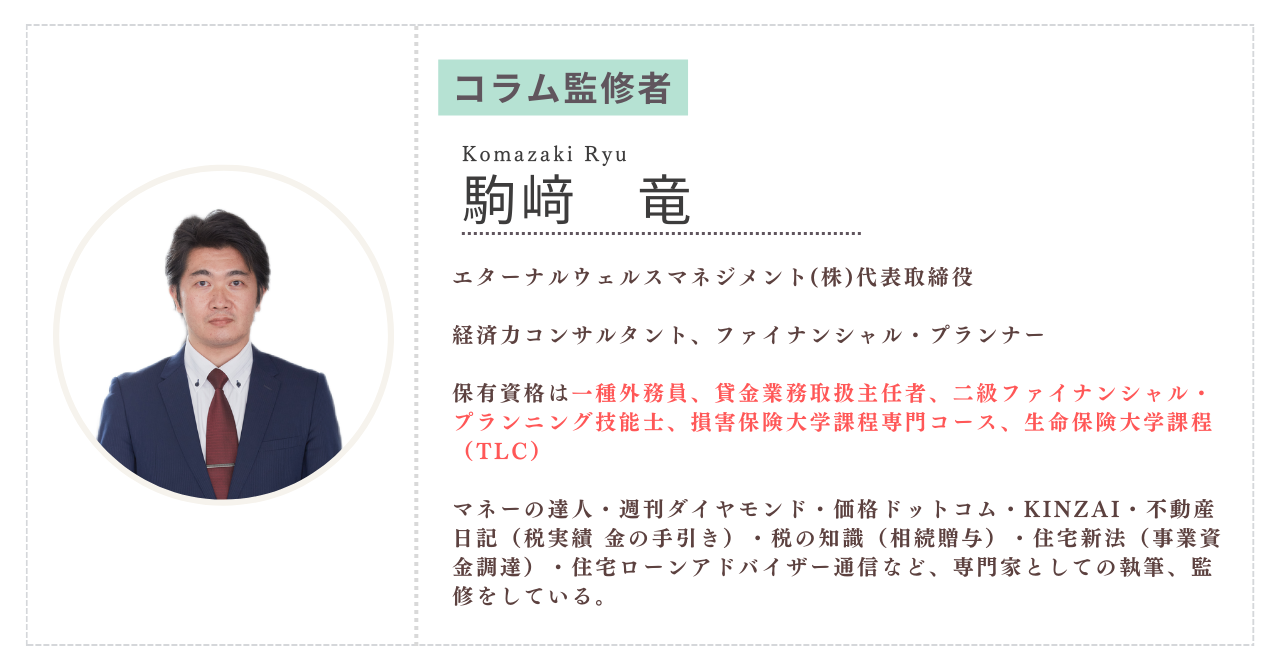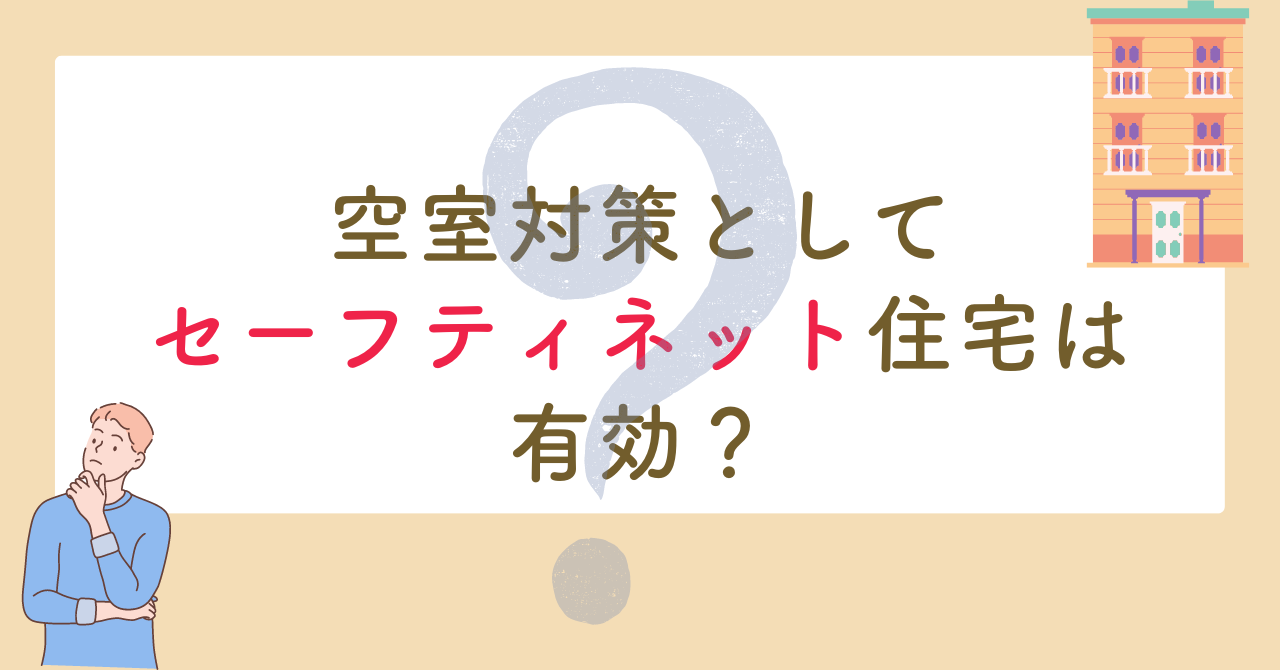
「住宅セーフティネット制度」をご存知でしょうか。2017年にスタートした公的な住宅支援で、不動産オーナーの中には、空室対策として利用している人もいます。
住宅セーフティネットとはどんな制度なのか、この制度を利用した場合のメリット・デメリットなど、この機会によく知っておきましょう。
住宅セーフティネット制度とは?

住宅セーフティネット制度は、高齢者や障害者、低所得者など、住まい探しに困っている人に住宅を紹介する公的支援制度です。この制度に登録された住宅を「セーフティネット住宅」といいます。
そもそも公的な住宅支援としては、1950年代から次々に建設された公営住宅がありました。家賃が安い公営住宅は、申し込んでもなかなか入居できないほど人気となっています。
しかし、人口が減少傾向で税収も上がらない中、今以上の公営住宅を建築することは難しいといっていいでしょう。一方で民間の賃貸住宅は、地方を中心に空家が増加傾向にあります。
そこで2017年に制定されたのが、住宅セーフティネット制度です。民間の賃貸住宅をセーフティネット住宅として登録してもらうことで、公営住宅と同じように住宅支援が必要な人に住まいとして提供する目的で整備されました。
セーフティネット住宅は、国が運営するウェブサイト「セーフティネット住宅情報提供システム」で探せるようになっています。アクセスや検索には、資格や登録などは一切必要ありません。
不動産オーナーが所有住宅をセーフティネット住宅にすれば、誰でも検索できるシステムに空室情報を登録してもらえるのです。有効な空室対策になると考えるのも当然でしょう。
セーフティネット住宅には2つのタイプがある
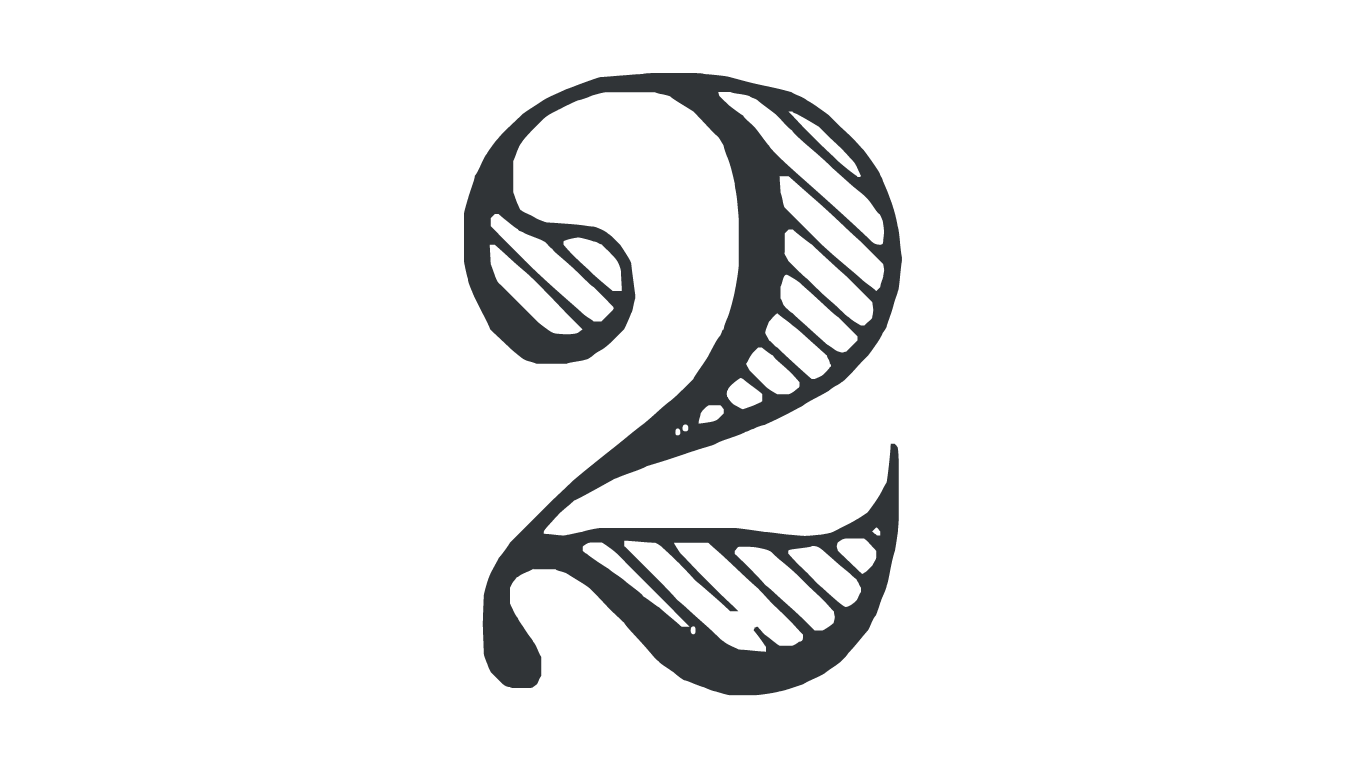
所有不動産をセーフティネット住宅にするには、自治体の窓口で「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅」として登録申請を行わなければなりません。また登録できるのは、以下の4つの条件を満たした住宅のみです。
・床面積25平方メートル以上
・耐震性がある平米以上
・キッチンやバストイレなどの設備がある
・家賃が地域の相場から大きく外れていない
セーフティネット住宅には「登録住宅」と「専用住宅」の2種類があり、どちらで登録するかは不動産オーナーが自由に選べます。ただし、登録住宅ならいつでも登録を取り消すことができますが、専用住宅なると10年間は登録を取り消すことができないので注意が必要です。
セーフティネット登録住宅は、住宅支援が必要な人の入居申し込みを拒まない住宅のこと。それ以外の人からも、入居希望があれば入居させても問題ありません。
セーフティネット専用住宅は、住宅支援が必要な人の専用となります。つまり、住宅支援が必要ない人からの入居申し込みは受け付けられないということです。
セーフティネット専用住宅にすると、耐震改修やバリアフリー改修などのリフォーム費用に対して最大50万円の補助金が受け取れます。また入居者に対する家賃補助もあるため、家賃が回収できないリスクも引き下げられます。
セーフティネット登録住宅には、家賃補助やリフォーム費用の補助はありません。そのため住宅支援を受ける人の間では、登録住宅より専用住宅のほうが人気となっています。
セーフティネット住宅のデメリット

セーフティネット住宅にするデメリットは、入居者トラブルが発生しやすいことでしょう。入居した人が低所得なら家賃の不払い、高齢者なら孤独死といったリスクが考えられます。
こういったデメリットをなるべく避けたい場合は、セーフティネット住宅への登録はおすすめできません。ただ、セーフティネット住宅なら登録住宅か専用住宅かを問わず、居住支援法人の入居サポートが利用できます。
居住支援法人は、「住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)」に基づいて組織された団体です。セーフティネット住宅のオーナーが不利益を被らないよう、入居者のフォローや手厚い見守りサービスを行っています。
空室対策として住宅セーフティネット制度を利用するなら、いきなり専用住宅にするのではなく、登録住宅から始めることをおすすめします。そして居住支援法人と連携し、少しでもリスクを引き下げたいものです。