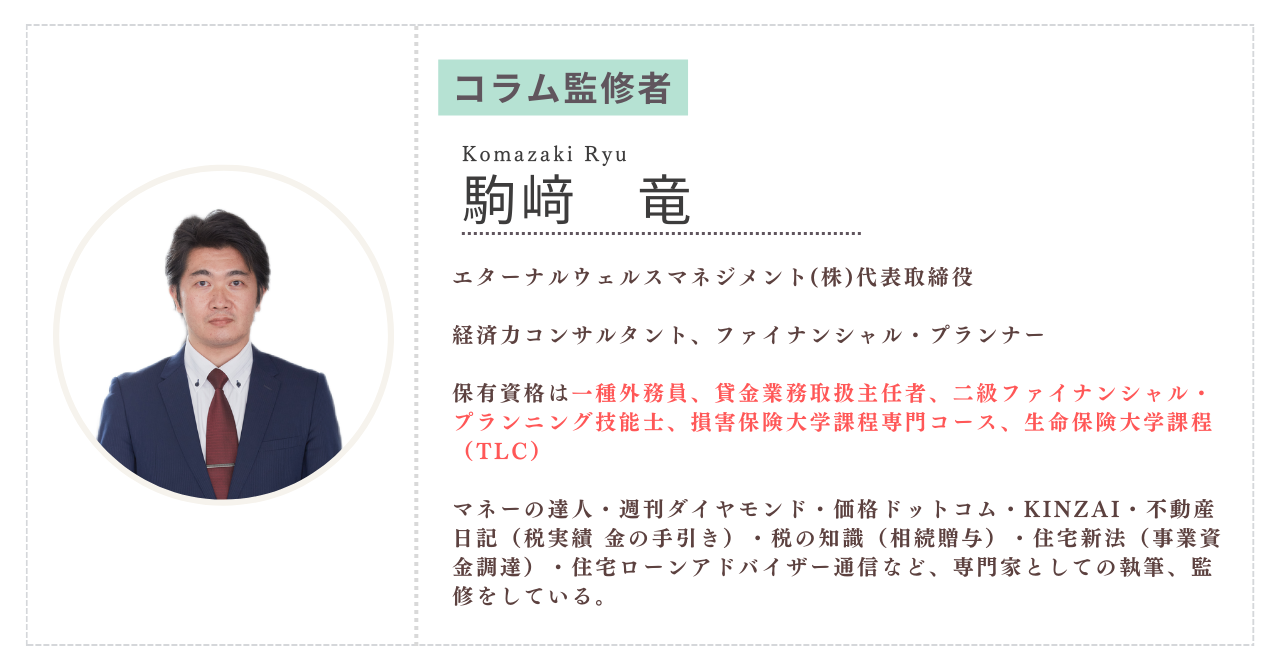これまで不動産投資は、相続税対策になるとされてきました。特にタワーマンションの上階は節税効果が高いため、「タワマン節税」といわれていたくらいです。
しかし2024年1月1日から施行された相続税法の改正で、状況は変化しています。どのように変わったのか、改めてチェックしてみましょう。
これまで不動産投資が節税になってきた理由
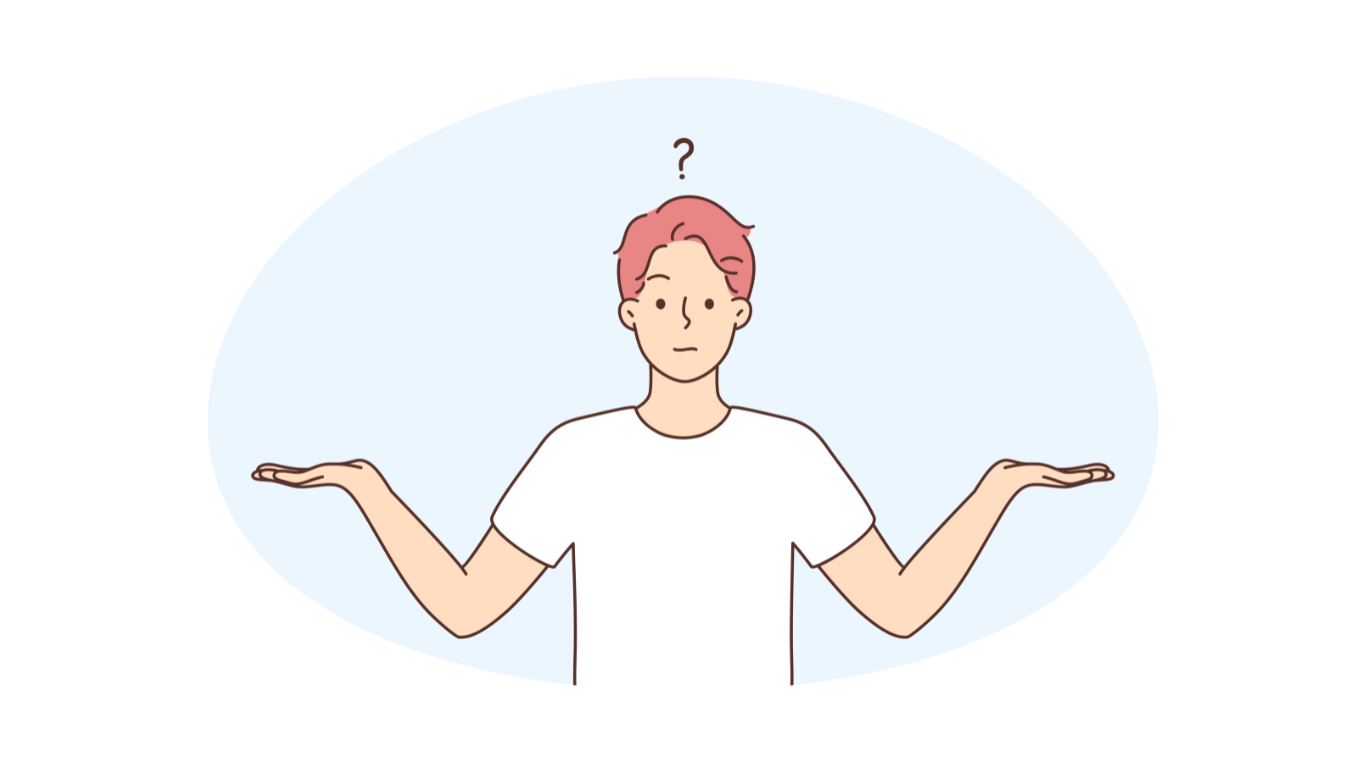
相続税法の改正ポイントを解説する前に、これまで「不動産投資は節税になる」といわれてきた理由を説明しておきましょう。
相続税額を計算する際には、故人が所有していた財産をすべて金銭に換算した「相続税評価額」を出します。相続税評価額から規定の控除額が差し引かれ、残った金額に対して相続税がかかる仕組みになっています。
不動産の相続税評価額は、時価ではなく固定資産評価額や路線価をもとに導き出されます。不動産の固定資産評価額は一般的に、時価の7割を基準に決められています。
時価5000万円の不動産なら、単純に考えて相続税評価額は3500万円前後ということ。つまり、5000万円を現金で持っているよりも、時価5000万円の不動産を持っているほうが、相続税が安くなるのです。
さらに固定資産評価額は、一戸建てよりマンションのほうが低くなる傾向がありました。その理由は、所有している土地の広さです。
土地付き一戸建ての場合、建物が建っている土地はすべて所有者1人の財産です。一方、マンションの場合は建物が建っている土地の権利を、マンション各部屋の所有者が分割して所有することになります。
住居そのものの面積が同じでも、一戸建てとマンションでは所有する土地の面積が圧倒的に違うため、マンションのほうが固定資産評価額が安く、相続税でも有利になるというわけです。
加えてマンションの場合、同じ建物にある同じ広さの部屋なら、低層階でも高層階でも固定資産評価額は同じです。しかしタワーマンションの場合、低層階と高層階では時価が2倍以上違うということも珍しくありません。
結果として、タワーマンションの高層階ほど時価と固定資産評価額のギャップが大きく、節税効果が高い状態が続いていました。そのため「タワマン節税」といった言葉ができてしまったのです。
2024年の相続税法改正で、節税効果は小さくなった

こういった時価と固定資産評価額のギャップを埋めて、加熱した相続税対策に歯止めをかけるべく、2024年から新ルールが適用されることになりました。2024年1月1日以降に相続した区分マンションについては、新ルールに従って相続税を計算します。
新ルールでは、まず相続税評価額と時価の「乖離率」を計算し、相続税評価額が時価の60%に満たない場合は、時価の60%まで相続税評価額を引き上げることになりました。
参考までに乖離率の計算方法をご紹介しましょう。まずは、下の4つの計算式で数値を出します。
1.マンションの築年数(1年未満は1とする)×△0.033
2.マンションの総階数÷33×0.239
3.部屋の所在階×0.018
4.マンション敷地の共有持分割合÷専有登記床面積×△1.195
1~4の数値の合計に3.22を足したものが乖離率となります。計算式を見れば、タワマン節税をターゲットにした新ルールであることが分かるでしょう。
ただ、以前より節税効果が小さくなったとはいえ、時価5000万円の不動産のほうが現金5000万円より節税になることに変わりはありません。相続税の節税対策として、投資用不動産は有効であるといえるでしょう。
ひとつ気をつけておきたいのは、相続した不動産を売却する場合のタイミングです。
投資用物件を相続してすぐに売却して現金化すると、脱税を疑われることも。疑惑を避けるためには、最低5年は保持してから売却することをおすすめします。