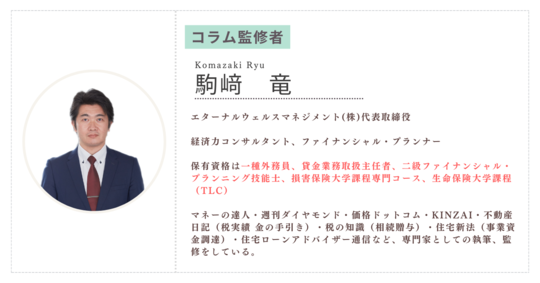相続した不動産、どうやって分割する?
2023年11月29日

遺産として家を相続する場合、相続人が複数いると、家を誰のものにするのかもめてしまうことがあります。かといって、家を相続人の人数で割って相続するのも、あまり現実的ではありません。
遺産として家が残された際、どんな分割方法があるのかご紹介しましょう。
家という現物を相続する4つの方法

金銭ではなく、家のような現物を遺産として分割するには、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法があります。それぞれ説明していきましょう。
現物分割は、財産をそのままの形で相続する方法です。相続人のうち誰か一人が家を相続し、金銭は別の一人が相続するといったように、家を壊したり売ったりすることなく相続します。
遺産分割では、現物はできる限りそのままの形で相続されるのが望ましいと考えられています。そのため現物分割が原則とされていて、裁判所での調停になった際もまず現物分割を勧められます。
代償分割は、相続人のうちの誰かが現物を相続した上で、ほかの相続人に対してそれぞれの相続分に相当する金銭を支払う方法です。たとえば3000万円の価値の家があり、相続人A・B・Cの3人が等分の相続権をもつとしましょう。
3人はそれぞれ1000万円分の権利がありますから、Aが家を相続するなら、AはBとCに1000万円ずつ支払うことになります。Aが、BとCに支払うべき合計2000万円を用意できなければ、代償相続は成り立ちません。
換価分割は、現物を任意売却や競売で現金化し、分配する方法です。遺産分割協議がもめてしまったケースでは、裁判所の審判で換価分割が行われることもあります。
共有分割は、複数の相続人が財産を共有する方法です。1つの家に対して3人の相続人がいた場合、3人がそれぞれ3分の1の権利を持つとして、共有名義で法務局の登記簿に登録します。
相続人全員の合意があれば、4つのうちいずれの方法でも選ぶことができます。また相続人全員が納得するなら、誰か一人が全ての遺産を受け継ぐといった不公平な相続もできます。
遺産分割協議がまとまらず裁判にまでもつれ込んだ場合、現物分割→代償分割→換価分割→共有分割の順で勧められることになるでしょう。
ただ共有分割にすると、自分の持ち分だけ売るといったことは難しくなります。家を補修するにも登記された所有者全員の同意が必要になるので、あまりおすすめできません。
遺産分割の際には相続税の申告期限に注意

遺産分割は「いつまでにしなければならない」という期限はありません。しかし相続税については、「相続が始まったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に申告する必要があります。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が終わっていればいいのですが、協議が1年以上にわたって長引くことも珍しくありません。そんな時はどうしたらいいのでしょうか。
期限内に遺産分割期評議が終わらなかった場合、民法で定められている相続権の割合に従って相続したと仮定して、相続人がそれぞれ相続税の申告をします。そして遺産分割協議が終わってから、実際の相続分に従って修正申告をするのが一般的です。
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、相続税に加えて無申告加算税などが課せられることがあります。遺産分割協議が長引いている時には、相続税の申告期限に注意しましょう。
ただ相続税には、相続人1人につき3000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除が認められています。簡単に言うと、自分が受け取る遺産額がおおむね3600万円以下なら相続税を申告する必要はありません。
遺産相続は、亡くなった人の思いを受け取るということでもあります。冷静によく話し合って、納得のいく形で遺産分割をしたいものです。