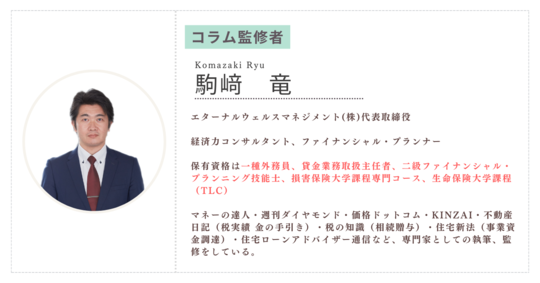入居者が亡くなった場合、次の入居者に告知する義務はある?
2023年11月24日
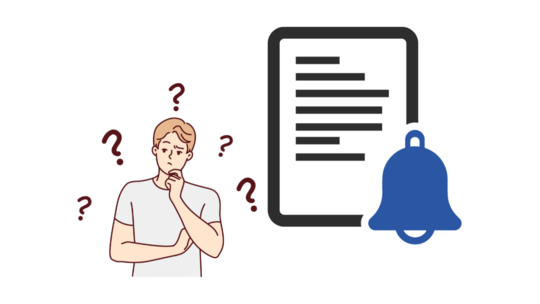
入居していた人が、居室内で亡くなってしまった……。賃貸住宅を運営していると、そういう事態は決して珍しくありません。
では、次の入居者を募集する際に、前の住人が部屋で亡くなったことを告知しなければならないのでしょうか。この機会に、告知義務のポイントをしっかり押さえておきましょう
亡くなった状況によっては告知の必要はない

宅地建物取引業法では「物件に瑕疵については、入居や購入を希望する人に伝えなければならない」と定められています。これを一般的に「告知義務」といいます。
居室内で人が亡くなった場合、物件の「心理的瑕疵」にあたります。ただし、亡くなった原因や状況によっては、告知する必要はありません。
以前は「いつまで告知しなければならないのか」といった細かい判断基準がありませんでした。そのために、「次の住人には告知するが、次の次の住人には告知義務はない」と解釈をすることも多かったようです。
告知の基準がはっきりしていないと、不動産取引に支障が出てしまいます。そこで国土交通省は、2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。
ガイドラインのポイントは、以下の3点です。
・自然死の場合は告知の必要はない
・自然死でも、遺体が長期間放置された場合は告知の必要がある
・死亡原因がはっきりしない場合は、告知の義務がある
ガイドラインでいう自然死とは、老衰や病死のほか、「浴室で滑って転倒した」「階段を踏み外して落ちた」といった日常生活での事故死も含まれます。つまり「家で人が死ぬのはごく普通のことなので、次の住人に伝えなくてもいい」ということです。
ただし自然死であっても、亡くなったことに気づかないまま遺体が長期間放置されていた場合は、告知の義務があります。「長期間」というのがどのくらいなのかは判断が分かれるところですが、いわゆる「特殊清掃」を依頼することになったケースと考えていいでしょう。
亡くなった原因が、自然死なのか事件なのかはっきりしない場合も、原則として告知の義務があります。もちろん、亡くなった原因が殺人や自殺など事件性のあるものだった場合は、告知の義務があります。
さらにガイドラインでは、告知すべき期間についても「おおむね3年間」と記されています。事件による死亡などで告知義務があるケースは、事件が起こってから3年間は、住人が何回入れ替わったとしても、そのたびに告知をしなければならないということです。
ガイドラインがあっても、絶対ではないことに注意

ひとつ注意しておきたいのは、ガイドラインは「このくらいが妥当ではないか」という目安であって、法律のように「絶対に守らなければいけない」ルールではない、ということです。
ガイドラインに沿っていれば、刑事責任を問われることはありません。しかし、前の住人が居室内で自然死したことを次の住人に告知しなかったら、後から事実を知った入居者がショックを受けて、仲介した不動産業者や物件オーナーを民事裁判で訴えた、といったトラブルが起こる可能性も。
訴えられたからといって、裁判で負けるとは限りません。ただ裁判になれば、最終的に勝てたとしても手間や時間がかかってしまいます。
特に、ガイドラインのポイントで挙げた「遺体が長期間放置された場合」など、人によって解釈の分かれる部分には注意が必要です。
不動産取引でのトラブルを避けるためには、個々のケースごとにオーナーと不動産業者でよく話し合い、告知するかどうかを決めたほうがいいでしょう。