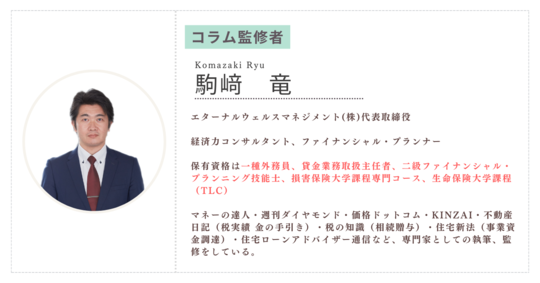不動産の賃貸契約や借地権は相続できる?
2023年10月18日
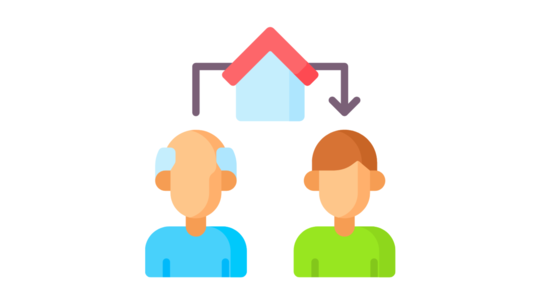
賃貸物件に家族で住んでいたのに、借主として賃貸契約を結んでいた人が亡くなってしまった……。そんな時、残された家族は家を追い出されてしまうのでしょうか。
住居の賃貸契約や借地権は相続できるのか、詳しくご説明します。
賃貸契約や借地権も相続の対象になる

結論から言うと、不動産の賃貸契約や借地契約は財産として相続できます。相続する際に、貸主である大家に許可をもらう必要はありません。
賃貸契約や借地契約の相続では、契約内容がそのまま相続人に引き継がれます。相続人と新たな契約を結ぶわけではないので、更新料を支払う必要もありません。
実は、借主が亡くなったことで大家から「家を明け渡してほしい」と言われたり、更新料を請求されたりといったケースも決して珍しいことではないのです。しかし法律では認められていないので、遺族が拒否してもまったく問題ありません。
相続人が複数いる場合には、いったん相続人全員が共同で相続する形となります。法律用語では、所有権以外の財産を共同で保有する場合は「準共有」といい、賃貸契約や借地権も準共有に当たりますが、意味としては共同で所有していると考えていいでしょう。
その後、相続人全員で遺産分割協議をして、いったん共同で相続した賃貸契約や借地権を、相続人のうち誰か1人が相続することもできます。例えば相続人が5人いて、そのうちの2人て準共有するといったことも可能です。
相続の時点で家賃の滞納があった場合は、その債務も相続人全員が共同で負担することになります。遺産分割協議が済むまでの期間にかかる家賃も、同じく相続人全員が負担しなければなりません。
最終的には、相続人それぞれの相続割合に応じて負担することになります。ただ一般的には、契約を相続することに決まった人が、滞納分や遺産分割協議までにかかった家賃を負担することが多いようです。
借主が亡くなっても、退去を求めるのは難しい

貸主である大家が、賃貸契約を結んでいる借主が亡くなったことを機に、遺族には退去してほしいと考えることもあるでしょう。しかし、遺族が「住み続けたい」と思っている場合は、かなり難しいといえます。
退去してほしい場合にはまず、契約期間が満了する6カ月前までに「契約更新をしない」と通知しなければなりません。つまり、退去してもらいたくても、契約更新時にしか退去を求められないのです。
通知したとしても、「退去を求めるだけの正当な事由がある」と認められなければ、法律によって賃貸契約が自動的に更新されてしまいます。退去を求める正当事由とは、例えば大家自身が住む、建物の建て替えの必要があるといった、やむを得ない理由です。それ以外はほぼ認められないと考えてもいいでしょう。
もちろん、家賃滞納などの重大な契約違反がある場合は、契約更新の時期を待たずに退去を求めることもできます。しかし家賃滞納も、1~3カ月程度では難しいと考えておきましょう。
住む場所がなくなるというのは、生活の基盤を失うということ。そういった状況に陥らないためのセーフティネットとして、賃貸契約や借地権は借主にかなり有利になるよう整備されているのです。
ちなみに賃貸契約や借地契約の相続は、内縁の配偶者や事実上の養子にも認められています。内縁配偶者とは、婚姻届は出していないけれど同居して夫婦のような生活をしている関係をいい、事実婚の夫婦なども内縁配偶者に当たります。事実上の養子も同様に、養子縁組届の提出はしていないけれど同居して親子のような生活をしている関係です。
ただし、内縁配偶者や事実上の養子が賃貸契約や借地契約を相続できるのは、ほかに相続人がいない場合に限られています。死去した人の親兄弟など、ほかに相続人がいる場合には、内縁配偶者や事実上の養子に相続権はありません。
契約していた借主が亡くなった場合、相続はどうなっているのか、貸主側からはなかなか聞きにくいことでしょう。しかし、家賃の請求先などを把握しておかないと、損をしてしまうこともあります。できれば早期のうちに、借主側の事情を把握しておきたいものです。