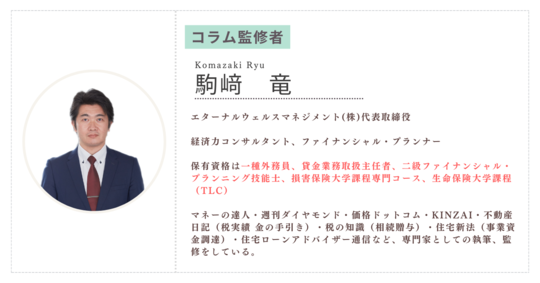住宅の固定資産税は、どうやって決められている?
2023年7月14日

不動産を購入すると、翌年から固定資産税を支払わなければいけません。固定資産税がいくらになるかは、所有している不動産の「固定資産税評価額」によって違ってきます。
その固定資産税評価額はどのようにして決められているのかご存知でしょうか。改めて、固定資産税評価額が決まる仕組みを押さえておきましょう。
固定資産税と固定資産税評価額と固定資産評価基準の関係

土地や建物といった不動産にかかる固定資産税は、「固定資産税評価額」に1.4%(一部市区町村では異なる)の税率をかけて算出します。計算の元となる固定資産税評価額は「課税標準額」とも呼ばれ、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算にも使われています。
固定資産税評価額は、土地や家屋を登記した際に1軒ごとに決められます。その金額を算出しているのは、各自治体の固定資産税評価員です。
もちろん、固定資産税評価員が独断で決めているわけではありません。評価員によって判断の差が出ないよう、「固定資産評価基準」という細かい判断基準が設けられています。
固定資産評価基準は、地方税法に基づいて総務省が告示しているものです。土地の広さや形、どんな風に道路に接しているか、建物ならどんな建材がどのくらい使われているか、どんな住宅設備があるかによって、それぞれの点数を定めた一覧表と考えておけばいいでしょぅ。
土地の場合はまず、地価公示法に基づいて国土交通省土地鑑定委員会が毎年公示する地価を元に、基準となる点数を定めます。そこに「道路に接している間口部分よりも、奥行きのほうが長いから、点数を97%に割り引く」といったさまざまな補正を加えて、最終的な土地の点数が決まります。
建物の場合は、新築後1年以内に評価員が1軒1軒を現地調査し、使っている建材や住宅設備について細かく検分して点数をつけていきます。その合計点数が高いほど固定資産税評価額が高くなり、固定資産税も高くなるという仕組みになっているのです。
固定資産税評価額は、固定資産評価基準によって不動産の価値を算出したもので、実際にいくらで売買されたのかは関係がありません。目安としては、土地は公示価格の70%程度、建物は建築費の50~70%程度になると考えておくといいでしょう。
固定資産税が上がりやすい住宅設備
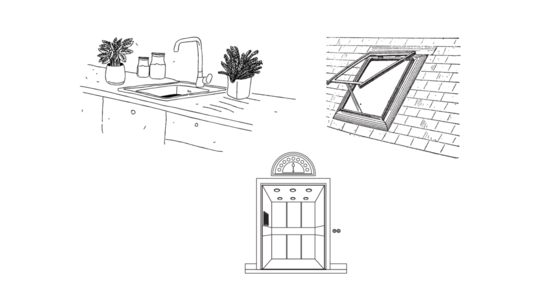
建物の固定資産税評価額は、使われている建材や住宅設備によって変わってきます。そのため、見た目がまったく同じ建物でも、内部の構造や備え付けられた設備によって、評価額が大きく変わってしまうことがあります。
固定資産評価額が上がる住宅設備の代表は、ホームエレベーターでしょう。ホームエレベーターがついているだけで1788000点が加点され、積載量が200kgを超える大型のホームエレベーターなら加点は1,966,800点になってしまいます。
キッチン設備では、ステンレス流し台なら51300点ですが、システムキッチンだと319200点、幅300cmを超えるシステムキッチンだと367080点となっています。洗面台も幅によって点数が異なり、標準的な洗面台なら66630点ですが、幅120cm以上は93282点となります。
天窓も、開閉できるかどうかによって点数が違ってきます。固定式の天窓なら63950点ですが、開閉式は106300点です。
ただし固定資産評価基準は、建築技術の進歩や時勢に合わせて随時改正されています。例えばドアホンは現在、カメラ付きのものが標準とされていて、通話しかできないものは標準点数の30%しか加点されません。
また固定資産税評価額も、3年ごとに見直しが行われます。土地は、見直し時点の公示地価によって評価額も変動。建物は経年劣化が加味されて、評価額が次第に下がっていきます。
固定資産評価基準は、総務省の公式サイトで公開されています。できるだけ固定資産税を安くしたいと考えるなら、詳しくチェックしてみるのもいいでしょう。