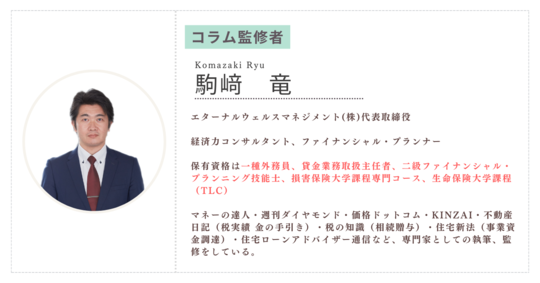不動産広告で見かける「旧耐震」と「新耐震」とは?
2023年6月14日
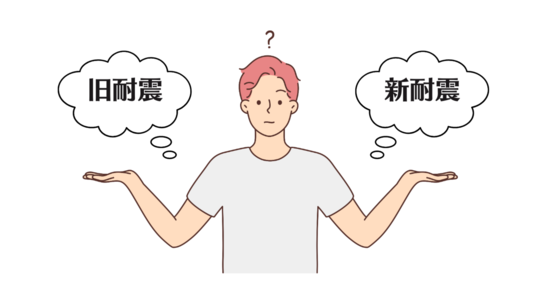
中古マンションの広告を見ていると「旧耐震」「新耐震」という言葉を見かけることがあります。どちらも耐震の基準を表していますが、どう違うのかご存知でしょうか。
この機会に、法律で定められた耐震基準について詳しく知っておきましょう。
耐震基準は、1981年6月1日を境に大きく変化
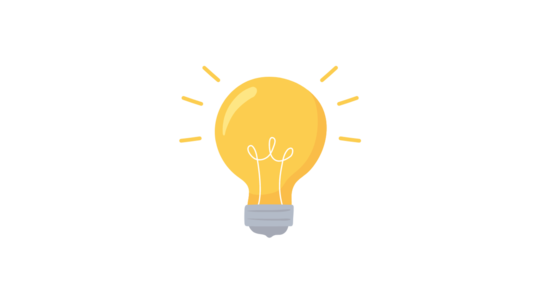
建物の耐震基準は、建築基準法によって定められています。そして建築基準法は、社会状況の変化や建築技術の進歩を受けて、ほぼ毎年のように細かく改正されています。
特に大きな改正が行われたのが、1981年(昭和56年)のこと。1981年6月1日施行の改正で、建物の耐震基準が引き上げられました。
それまでの耐震基準は、「震度5程度の地震が来ても、建物が倒れないこと」という内容になっていました。また、震度6以上の地震については言及されていません。これがいわゆる「旧耐震基準」です。
しかし1981年6月1日の改正では、「震度5程度の地震では、建物が損傷しないこと」となりました。さらに「震度6~7程度の地震が来ても、建物が倒れないこと」という内容が加わったのです。これが「新耐震基準」で、現在でも耐震基準のベースとなっています。
旧耐震基準から新耐震基準に改正されたきっかけは、1978年(昭和53年)に起こった宮城県沖地震です。この時、仙台市では震度5を観測しましたが、建物が崩れて大きな被害となりました。その教訓から、耐震基準が引き上げられたのです。
見分けるポイントは「建築確認通知書の日付」

1981年6月1日を境に、耐震基準が大きく変わったと言いました、気をつけなければいけないのは、旧耐震と新耐震のどちらの基準に従って建てたのかは、建物が完成した竣工日ではなく、着工日で決まるということです。
1981年6月1日以降に完成した建物でも、着工日が1981年6月1日より前の場合は、新耐震基準に従う必要はありません。ですから、建物が旧耐震か新耐震かを知りたい場合は、着工日を調べる必要があります。
とはいえ、いつ着工したのか正確な日付を知るのはなかなか難しいもの。その時にポイントとなるのが「建築確認通知書の日付」です。
建物を建てる際には、事前に自治体に建築確認申請をして、建築基準法にのっとった建物かを確認してもらわなければなりません。確認が済むと建築確認通知書(現在の名称は「建築確認済証」)が発行され、着工となります。
つまり、正確な着工日が分からなくても、建築確認通知書の日付が1981年6月1日以前なら旧耐震基準、以降なら新耐震基準の建物ということになります。
木造住宅に適用される「2000年基準」

建築基準法の耐震基準は、2000年(平成12年)6月1日にも改正されました。これは木造建築物についての改正で、鉄筋コンクリート造など木造以外の建築物は関係ありません。
この改正は、1995年(平成7年)に起こった阪神淡路大震災の被害を受けて行われました。内容としては、直下型地震に備えるために基礎の設計や工事をより強固にするといったもので、「2000年基準」と呼ばれています。
中古木造住宅を購入する場合、2000年6月1日以降に着工した建物なら、より安心といえるでしょう。
ひとつ注意しておきたいのは、建築基準法はあくまで「最低でもこれだけは守らなければいけない決まり」でしかないということ。改正前に着工したにもかかわらず、新耐震基準を満たしている建物は少なくありません。
旧耐震基準で建てられた古い建物でも、耐震補強工事を行って新耐震基準以上の耐震性能を得ることもできます。反対に、新耐震基準の建物であってもメンテナンスを怠れば、耐震性能はどんどん下がってしまいます。
中古住宅を購入する場合は、旧耐震か新耐震かだけに気をとられることなく、メンテナンスの状況や地盤の安全性などにも目を配りたいものです。現在の耐震強度がどのくらいなのかを詳しく知りたい場合は、専門家による耐震診断を行うことをお薦めします。