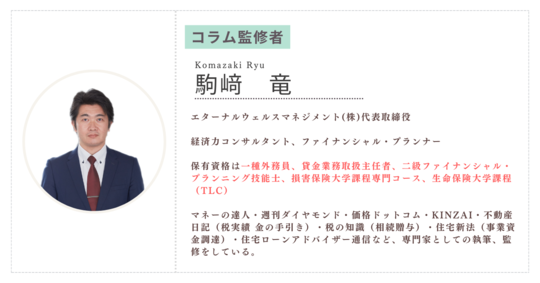マイホーム前にある邪魔な電柱、場合によっては移設できるかも?
2023年3月31日
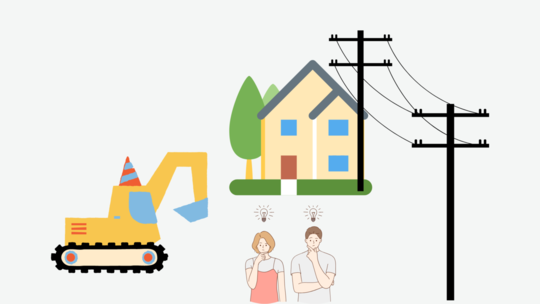
家の前に電柱が立っていると、車が出入りしづらいなど日常生活に支障を来すことがあります。
電柱は公共物なので、撤去や移設は難しいと思ってはいませんか?
実は、条件さえ整えば電柱の位置を動かしてもらえます。電柱の移設・撤去について、詳しく見てみましょう。
敷地前の電柱は、条件を満たせば移設できる
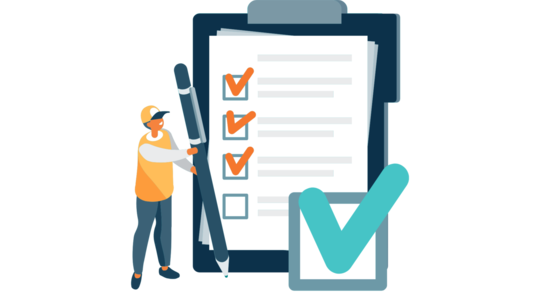
結論から言うと、公道上(敷地外)にある電柱の移設場所として、敷地の一部を提供するなら、比較的簡単に移設できます。すでに敷地内にある電柱を、敷地の別の場所に移すことも、それほど難しくありません。
ただし、「敷地の東端にあった電柱を、西の端に移したい」といった、極端に場所が変わってしまうような場合は、移設を拒否されてしまうことがあります。ケースバイケースなので、まずは電柱の管理者に相談してみましょう。
難しいのは、公道上の電柱を別の公道上に移す、あるいはすでに敷地内にある電柱を公道上に移す場合です。いずれも移設先の道路管理者の許可が必要なので、許可が下りなければ移設できません。
中には、すでに使われていない古い電柱が、撤去されず残っていることもあります。その場合は電柱の管理者に連絡すれば、撤去してもらえます。ただ、使用中かどうか見た目からは判断がつかないこともあるので、まずは電柱の管理者に確認してみましょう。
電柱はどこが管理しているのか

電柱と一口に言っても、実は3種類あるのはご存知でしょうか。
ひとつは東京電力や関西電力などの電力会社が、各家庭に電気を送るために設置している柱で、正式には「電力柱(でんりょくばしら)」といいます。
もうひとつは、NTTなどの通信会社が電話やインターネットを各家庭に繋げるためのもので、正式には「電信柱(でんしんばしら)」といいます。
そして3つめは、電線と通信線の両方がかかっている「共用柱(きょうようばしら)」です
ほとんどの電柱には、どの会社が管理しているのかを示す管理プレートが取り付けられ、電柱1本ごとに割り振られた「電柱番号」が表示されています。共用柱の場合は、電力会社と通信会社の両方の管理プレートが取り付けられているので、見ればすぐにわかることでしょう。
電柱を移設したい時は、管理プレートに書かれている電力会社や通信会社に連絡します。電柱のある地域と電柱番号を伝えると、すぐにどの電柱か分かってもらえます。
共用柱では、管理プレートを取り付けている会社すべてに連絡をする必要があります。ちなみに、関東では下に取り付けられているプレート、関西では上にあるほうのプレートに書かれている会社が、電柱の所有者となっています。
電柱の移設にかかる費用や時間

電柱は、簡単には倒れたりしないよう、地中5メートルほど埋設してあります。そのため移設となると、かなり大がかりな工事になり、費用も20~35万円ほどかかります。
移設費用を誰が払うのかは、ケースバイケースといっていいでしょう。道路から敷地内への移設や、敷地内から敷地内への移設の場合、多くは電柱の管理者が費用を負担してくれます。
道路から道路への移設では、電柱や道路の管理者が負担してくれる場合もありますが、移設を希望した申請者の全額負担、あるいは道路の管理者と折半になることも。
使われていない電柱の撤去の場合、工事費用は移設よりも安く、10~20万円程度で済みます。ただし、撤去を申請した人が工事費用を負担しなければならないことがほとんどです。
電柱の移設や撤去の工事そのものは、1~2日程度で終わります。しかし、その前にさまざまな調整や打ち合わせが必要になるので、申請してから工事完了まで2~3ヶ月はかかると考えておきましょう。
敷地内に電柱があると使用料がもらえる

実は敷地内に電柱があると、電柱の管理会社から電柱敷地料(土地使用料)がもらえます。金額は1年間1500円で、3年ごとにまとめて支払われることがほとんどです。
電柱敷地料は「電気通信事業法」で決められているため、電柱管理者がどの会社でも金額は変わらず、物価や消費税率の変化にも左右されません。ちなみに年額1500円というのは宅地の場合で、田んぼなら1870円、畑は1730円、山林などは215円となっています。
電柱の立っている土地を購入した際には、電柱を管理している会社に届け出る必要があります。電柱使用料をもらい損ねないためにも、きちんと届け出をしましょう。