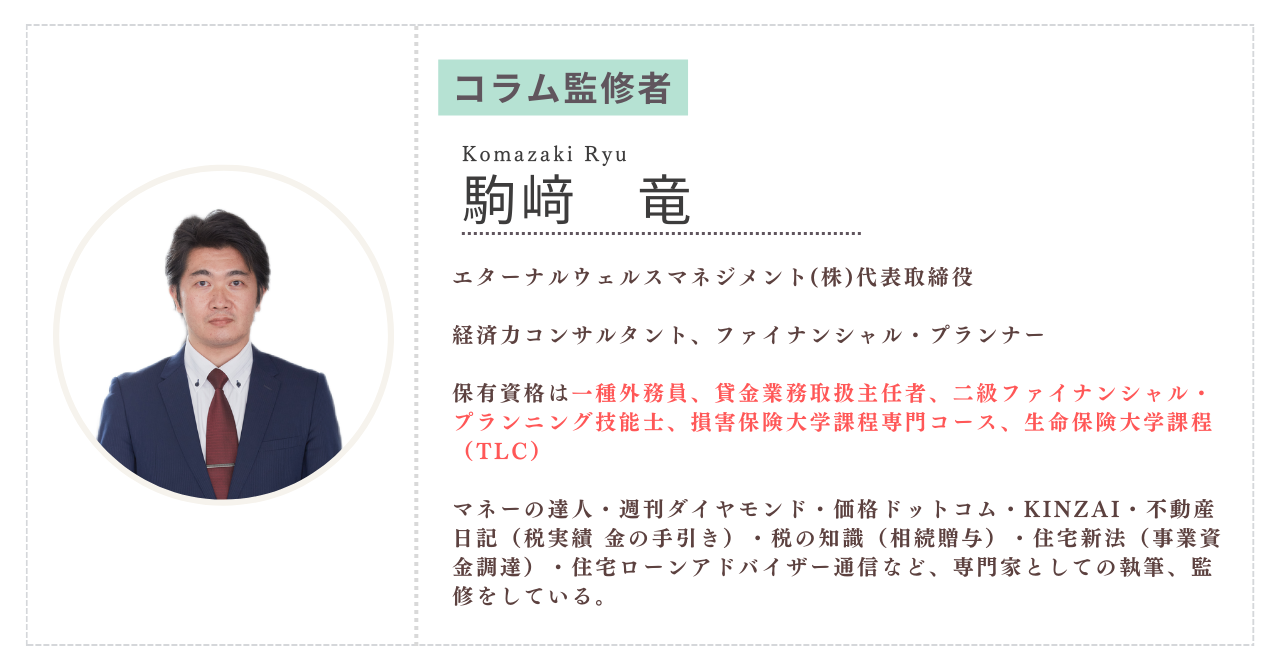坪単価とは? 知っておくと物件の比較に便利
2023年3月22日

坪単価とは? 知っておくと物件の比較に便利
不動産の広告を見ていると、「坪単価」という言葉を目にすることがあります。
坪単価は価格を表す情報のひとつで、知っておくと物件を比較検討する時に役立ちます。この機会に、坪単価の計算方法や使い方などを改めて押さえておきましょう。
坪単価とは、1坪あたりの建築費
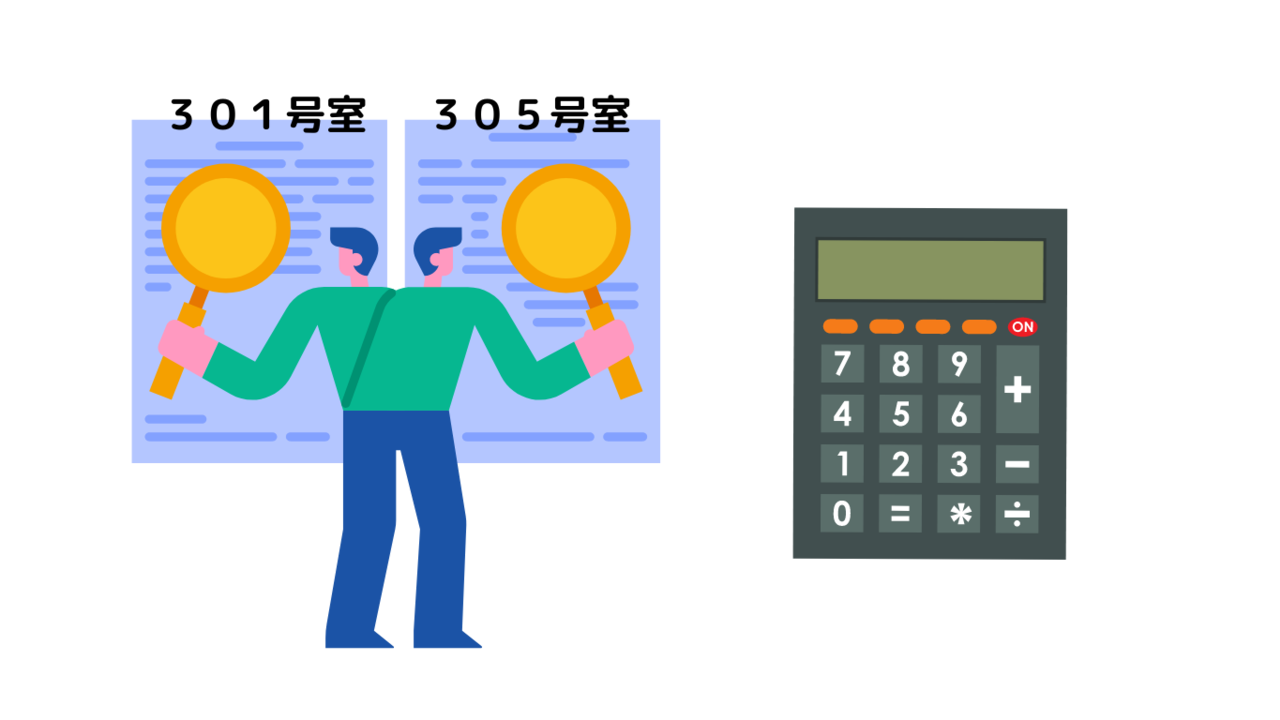
坪単価とは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの価格を示すものです。計算式は「価格÷面積(坪)=坪単価」となります。
坪単価は、広さの違う物件同士の価格を比較する時に便利です。例えば同じマンション内で2つの部屋があり、どちらを買うか迷っているとしましょう。
301号室 60平方メートル(約18坪) 3500万円
305号室 70平方メートル(約21坪) 4000万円
販売価格だけを見れば、305号室のほうが高値です。でも坪単価で比較するとどうでしょうか。
301号室 3500万円÷18坪= 約194万円/坪
305号室 4000万円÷21坪= 約190万円/坪
1坪という同じ面積あたりの価格は、305号室のほうが安くなっています。つまり、305号室のほうがお買い得といっていいでしょう。
もちろん部屋を購入する際には、単純に価格だけでは決められません。また、室内のリフォーム状況などによって、同じ部屋であっても価格は変わってきます。しかし、物件を比較検討する際の情報のひとつとして、坪単価が役立つことはお分かりいただけたのではないでしょうか。
なぜ「坪」という単位が使われているのか

現代では長さをはかる単位として、センチメートル、メートル、キロメートルといった「メートル法」が一般的になっています。しかし建築・不動産業界では、昔ながらの「間(けん)」「尺(しゃく)」といった「尺貫法」がよく利用されています。
1間は約1.8メートルで、畳の長辺とほぼ同じ長さになっています。畳の短辺の長さは、1間の半分で「半間(はんげん)」といいます。1尺は1間の6分の1の長さで、約30センチメートルです。
そして、1間(約1.8メートル)×1間(約1.8メートル)の広さが1坪(約3.3平方メートル)。畳2枚分とほぼ同じ広さです。
尺貫法は日本人の体格をベースに定められたといわれていて、畳1枚の広さがちょうど成人1人が収まるサイズになっています。じつは畳の大きさだけでなく、住宅のさまざまな場所が尺貫法を基準に作られているのです。
今は日本人の体格が向上したことで、広い廊下や背の高いドアや窓も多くなりましたが、昔は廊下の幅が半間、ドアや掃き出し窓の高さは1間が標準的でした。そういったことから、建築・不動産業界では未だに尺貫法が愛用されているのです。
一戸建ての坪単価は計算方法によって変わってくる

坪単価は、一戸建ての建築費を比較する際にも使われます。「建築費÷床面積(坪)」で、1坪あたりどのくらいの建築費がかかったのかを知ることができます。
まったく同じ外見、同じ広さの家でも、高級な建材を使っていれば坪単価は高くなります。つまり坪単価を見れば、家のグレードを知ることができるのです。
ただし、一戸建ての坪単価を見る場合には、気をつけなければいけないことがあります。それは、床面積が「延床面積(のべゆかめんせき)」なのか「施工床面積」なのかです。
延床面積は居住スペースの広さのことで、玄関ポーチ、ベランダ、小屋裏収納は含まれません。施工床面積は建物すべての床面積をいいます。そのため同じ家でも、延床面積より施工床面積のほうが広くなります。
当然のことながら坪単価も、延床面積で計算すれば高くなり、施工床面積で計算すれば安くなります。その結果、家のグレードをより高く見せるために、あえて施工床面積ではなく延床面積で坪単価を計算するといったことも行われています。
坪単価は便利な情報ではありますが、どうやって計算しているのかを知っておかないと、惑わされてしまうことも。その上で、物件選びの参考情報のひとつにしたいものです。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~17:00(日曜10:00~15:00)
※火曜・土曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
エターナルウェルス
マネジメント株式会社
住所
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-17
丹生ビル3階
アクセス
銀座線・東西線日本橋駅より徒歩1分
JR東京駅八重洲北口より徒歩5分
駐車場:近くに有料パーキングあり
受付時間
10:00~17:00(日曜10:00~15:00)
定休日
火曜・土曜・祝日